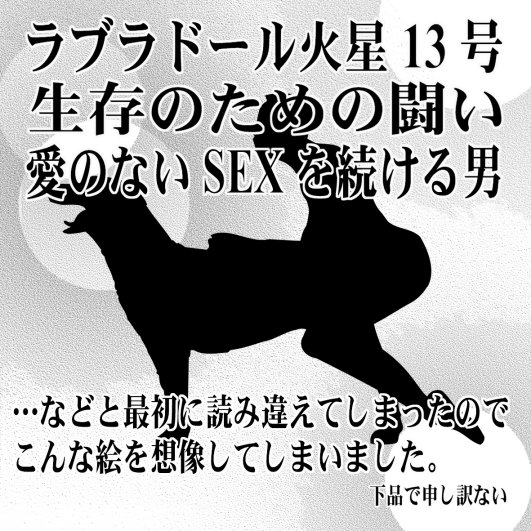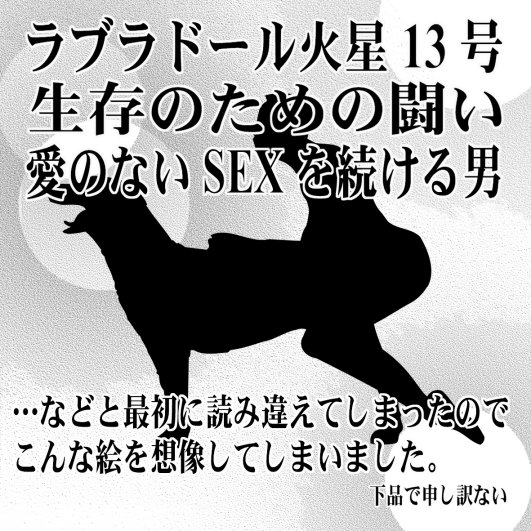
まぁ、内容がないようなので某出版社の某中間小説雑誌としておきましょう。そこに短編小説を書くことになった。
タイトルは「ラブドール火星13号――生存のための闘い、愛のないSEXを続ける男」というもの。タイトルだけで内容がわかるとっても親切なハードSFです。
しかし、親切と思ったのは私だけだったらしく、さっそく担当編集からメールが届く。ちなみにこの担当編集というのは、若い女性であって某有名大学の露文科に進み「ドストエフスキーにおける宗教観とファンタチカ性」が卒論という才媛である。
ちなみにファンタチカというのは、彼女によるとファンタジーとは別物で――ファンタジーはファンタチカという大集合の部分集合、ちなみにロシア文学ではSFも同様――純文学以外のカテゴリーらしい。ただこの純文学も日本とロシアでは意味が異なるそうである。
ともかくそういう女性であるから、人の親切がわからない。で、無粋とは承知しながらも親切の意味を教えねばならない。私はさっそくメールで返事を出した。
ちなみにこの短編の内容を紹介すると……。
21世紀の比較的早い時期。日本の宇宙飛行士が、火星基地に単身赴任することになる。基地自体は無人のロケットですでに打ち上げられており、彼はそこに赴任する。
そして背景とか色々あるのだが、この宇宙基地の動力は火星13号というラブドールから供給される。そしてラブドールの内部にはマイクロブラックホールがあり、これが蒸発しないように主人公はSEXを続けるのである……。
こういう単純な話である。説明などいまさら不要なはずである。にも関わらず、担当編集者からすぐに返事が来た。質問の返事。しかもメールではなく電話だ。
「あの短編なんですけど、ようするに最先端科学の非人間性を描いたわけですよね」
私自身は単なる馬鹿SFを書いたつもりなのだが、露文科を出ているせいか、どうも彼女は物事をバイアスをかけて見てしまうらしい。そういえば東海林さだお氏も何かのエッセイで露文科のそういう傾向を書いていたな。
「いえ、そういうわけではないのですが。それに最先端技術が常に非人間的とは限らないでしょう。ホーキング博士だって先端技術のおかげで自らの学説を発表出来たわけですしね」
ここで彼女の論理回路はすぐに別の解答を導き出したらしい。
「なるほど。つまり国家権力が個人の人権をもてあそぶ現実を小説の形で告発なさっているわけですね」
何かすごく不安になってきたのでとりあえず話だけは合わせることとした。
「そうです」
これで話は終わったかと思ったが、こんなのは挨拶代わりであった。
「ところでいただいた原稿に幾つか不明な点があるのですが」
「何でしょうか?」
「ええとですね……」
こういう時、何が嫌と言って、電話口で明らかに複数の紙をめくるような音が聞こえる時ほど嫌な物はない。質問数は紙の枚数に比例する。
「まず……」
そう、まずというのは質問が複数あるという意味の枕詞である。
「どうしてブラックホールからエネルギーが取り出せるんですか?」
「マイクロブラックホールですから」
「でも、ブラックホールでしょ?」
「だけどマイクロですよ」
1989年に早川書房の「ホーキング宇宙を語る」は当時、物理学の本がミリオンセラーになったことでも話題になった本だ。だからホーキング輻射によりマイクロブラックホールは熱いというのは、すでに常識であるはずなのだが、どういうわけかいまだにブラックホールは何でも吸い込むというイメージを持っている人は多い。じゃあ、あのミリオンセラーは何だったのだろうと思うのだが、現実は現実だ。
ここでしばらくホーキング輻射の説明を続けかけたが、センター試験は生物と化学、大学の二次試験は面接と小論文という件の女性編集者は、そもそも質量という単語をわかってくれない。正確には質量と重量の違いが伝わらない。
そこで戦術を転換した。ロシアにはロシアなりの攻め方がある。
「じゃあ、いままでの話は忘れてください。ブラックホールの大小を資本の大小と考えましょう、いいですか?」
「つまり太陽の数倍の重量のブラックホールは資本家で、原子核ほどの大きさのマイクロブラックホールはプロレタリアートのような存在と言うことですか?」
そう、彼女は知識はないが頭の回転は速いのだ。
「ええ、そう考えてください。つまり人間ですね、資本家になると貯めるだけで、社会に還元しようなんて微塵も考えない。しかし、プロレタリアート階級は、持てざる階級として、自らの資産を社会に還元しようという高い社会性と倫理観を持っている。
社会の進化が必然であるように、唯物史観は宇宙でも適応されます。故に巨大ブラックホールと違って、マイクロブラックホールからは強い放射があるのです」
我ながらいい加減な説明だと思う。しかし、彼女はこの説明でマイクロブラックホールのホーキング輻射について科学的には間違ってるが、絵的には正しい認識を持ってはくれた。いいんです、絵的に正しければ、挿絵はそれなりになるんだから。
「で、次の質問ですが……」
「えっ……」
すでに一五分にわたり全身全霊を傾けていい加減な説明をしてきたが、それで解決したのはまだ一つ。
「どうして主人公はブラックホールに対して射精し続けなければならないのでしょうか?」
「ええぇぇぇとですねぇぇぇぇ」
これは物理的には単純な話。ホーキング輻射を続ければ、続けるほどブラックホールは質量を失う。そうなるとホーキング輻射は急激に増大し、それがまた質量の減少を生む。放置すればマイクロブラックホールはある段階で大爆発を起こす。
これを防止するためには、マイクロブラックホールの質量を一定量に維持しなければならない。制御としては自転車操業を強いられる方法だ。
ちなみにこのマイクロブラックホールによるエネルギープラントの基本構造を考えたのはハードSF作家の小林泰三氏で、宇宙作家クラブの大阪例会でのこと。システムの構成案については私も多少かかわっている。
短編では主人公はラブドールのマイクロブラックホールの質量を維持するためにSEXを続け、射精し続けなければならない。そうしないとブラックホールの暴走で基地ごと蒸発してしまうのだ。
もっとも最終的に主人公は適正な質量さえ供給し続ければ射精をする必要がないことに気がつき、ラブドールの局部に(以下三行省略)である。
が、この原理を彼女はよく理解出来ないらしい。ブラックホールを資本家とプロレタリアートなんて大嘘をついて説明したばかりに墓穴を掘った形になった。それでも大脳の認識とは別に、嘘は出てくるものである。
「それはメタファーです。プロレタリアート階級がなぜ無限にエネルギーを出し続けられるのか? 巨大なブラックホールよりも弱者である彼らが何故?
それは新しい覚醒した世代が、彼らのあとに続いているからです。巨大なブラックホールは最終的に蒸発し、この宇宙から消えて行くでしょう。しかし、新しい世代がプロレタリアートの列に続く限り、それらは不滅なのです。射精とはつまり新しい世代、覚醒した人類の象徴なのです」
「なるほど!」
こういうやりとりがこの後2時間続いた。どうも担当編集者の頭の中では、この馬鹿ハードSFは何かもっと別物へと変容しているらしい。
「最後ですが……」
あぁ、私はこの言葉を待っていた。
「このラブドールなんですけど、ダッチワイフのことじゃないんでしょうか?」
もちろんダッチワイフである。いやじっさいにはいまのラブドールはマイコン制御もなされ昔のダッチワイフとは意味が違う。フェチズムの多様性も違うのだ。しかし、さすがにそれを資本家と労働者で説明する気力はなかった。
「まぁ、そうですけど」
「だったらラブドールよりもダッチワイフの方がわかりやすくありませんか?」
「えっ、知らないんですか?ダッチワイフは使ってはいけない言葉なんですよ。トルコ風呂がトルコ政府の抗議でソープランドになったように、ダッチワイフはオランダ政府の抗議により廃止されたんです。だからラブドールなんですよ今は」
「そんな話があったんですか……」
さすがに禁止用語については不審に思ったらしい。だが万が一と言うこともある。それにいままでの説明で、私は彼女に対して何やら絶大な信頼を受けているらしい。
「だったらラブドール(ママ)としておきましょうか?」
「はい、お願いします」
こうして私はラブドールという単語の改変をすることなく「ママ」で済ますために嘘をつき通したのでありました。