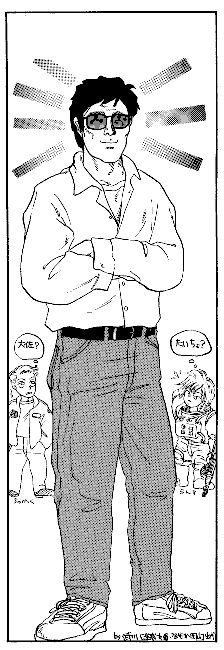
土方の私
三人の私がいる。土方の私、SF作家の私、そして山屋の私。高校生のころから、いつもこの三人が勝手に歩いていた。ネパールに行ってからさらにそれがひどくなった。
「生返事をしている内に、他人に人生を決められる」という言葉があるが、ネパールで協力隊員をしていた時期をはさんで、前後の数年間の私がまさにそれだった。
本当のことを言うと、“協力のなかの青春”ということで書くのだが、隊員として活動したことは紙数の関係上、あまり書けない。現役中に報告書を二〇〇ページほど書いたから、興味ある人はまたの折にも読んでほしい。そこでこれから書くことは、四〇〇〇名余の派遣隊員の一人が書いた“どこにでもいる協力隊バカの青春”と解されればいい。
高校生のころ“俺は土方になろう”と決めた。別に深い理由があったからではない。親父の仕事にも関係ないし、知り合いにも土方はいない。ただ青年海外協力隊の存在を知ったのが同じころだから、多少は影響があったと思う。も
っともそれだけじゃないんだが……。
高校生のころから(今でもそうだが)私は自分を土方と考え、そしてそれを誇りに思っている。自分の職業を聞かれたら、日本語なら迷うことなく土方、英語ならシビル・エンジニア(文明技術者)と名乗る。田中角栄ではないが“土方は地球の芸術家”なのだ。あのころの私にとって世の中で一番尊い職業は“百姓”であり、二番目は“土方”だった。
私が今よりも、もっとガキだった高校生のころには、いつも不思議で仕方がなかった。ホワイトカラーなんていう人々は、なんて可哀相なんだろう。一日中机の前で仕事をしていて、一体何が楽しいんだろう。太陽の下で仕事をしている百姓と土方をうらやましく思いすぎて、自分が嫌にならないんだろうか。
高校生のころには、こんなことを本気で考えていたのだ。
大学を卒業したての最初の三年半は、千葉県の片田舎の現場で施工と測量と
設計をやっていた。あのころは実によかった。“物を生産する”ということが、
こんなに楽しいものだとは知らなかった。世界が違ったものに見えた。図面を
じっと見つめて、平面図が立体的に浮かび上がって見えれば一人前なんだと、先輩に教えられ、初めてそう見えた時のうれしさ。最初は、年季の入った土方のおっさん連中に、大学出たての青二才としてしかあつかわれなかったのが、彼等との会話の中から土方の符牒を盗み出しては自分でそれを使い、気がついた時には「同じ土方」と言われるようになっていた。
休日は月に二日だけ、それだって忙しい時には直前に取り消されたりしたが、
仕事は充実していた。いつも、自分の仕事にほこりを持っていた。
そんなほこりがつき崩されたのは、一九七六年の秋ごろ、東京の街中に転勤になり、下水工事をするようになってからだった。
ひどかった。
本当のことを言うと、あのころのことなんて思い出したくもない。思い出すたびに腹が立って仕方がない。土方の尊厳もへったくれもない。都会のまん中で仕事をしていると、土方なんていかにみじめなものか身にしみてわかった。
下町のゴミゴミした通りで工事をしていると、いつも苦情が来る。別に苦情が出たってかまわない。出て当然だろう。しかし、一番嫌だったのは、地元住民が我々を小馬鹿にしたような態度でしか、口をきいてくれなかったことだ。
そのころの私は、少しは大人になっていたから、土方の方がお前らより偉いなんて言うつもりはない。だけど苦情を言うのになんであんなに頭ごなしに怒鳴りつけてくるんだ。なまじ、私が大手の会社の職員でひたすら頭を下げている内に、私は地域住民の欲求不満のはけ口になってしまったようだ。
弱い者は自分より弱い者を見つけて安心すると言う。下町の弱き庶民よりも
さらに我々は下層の階級だった。判官びいきなんていう勝手な論理の埒外に土
方はあったのだ。
悪い時には重なるもので、そのころ工事の最大の孫請け(事実上の下請け)が“ケツを割り”、年の暮れには事実上のジョイント・ベンチュアである下請け会社が倒産した。工事の竣工検査の一ヶ月前のことだった。
それからというものは、仕事の量が無茶苦茶にふえた。検査直前の、一番くそ忙しい時に非常識なほどの小人数の技術者で、仕事を全部片付けなければならなかった。正月をはさんで三ヶ月間だたの一日も休日はなかった。三十六時間ぶっ続けで仕事をやったことも珍しくない。飯を食いながら工事の打ち合わせをし、自由な時間はひたすら寝ていた。一分も一秒も無駄にせず、眠りたか
った。
別にあのころの仕事が重労働だと文句を言うつもりではない。人糞のぷかぷか流れて来る下水管に潜り込んで、汚れ仕事をしていることを、他人に感謝してほしいとも思わなかった。ただ、俺達も人間だということを知ってほしかった。苦情ばかり持ち込んで来る人々に。
そんな状態の中で、当然のように検査は不合格となり(億単位の赤字を出しながら)、再検査も不合格となった。地元住民の苦情に加えて、施主である東京都職員の顔が鬼に見えた。提出図面や、工事写真は何度も差し替えを命ぜられ、やってもやっても仕事は終わらなかった。やっと終わった工区が、ささいなミスでやり直しを命ぜられ、やったばかりの舗装をぶち壊して、埋設したての管を入れ替えるなど、しょっちゅうのことだった。
あのころの自分は相当すさんでいた。ささいなことから同僚と喧嘩し、結局、救急車を呼ぶ騒ぎとなったのもあのころだった。事務所には倒産した下請け会社の債権者が、いつもうろうろしていた。
借り物の自転車で駅前商店街を走っていたら、警官に自転車泥棒と間違われ、
交番に自転車を差し止められたまま、一時間後に“釈放”された。疑いが晴れたら、自転車を届けると言っていた警官から、その夜に電話があった。「引き取りに来い」
もしも私が汚れた作業服でなく、背広を着ていたらあんなことはなかったろう。
地平線を見た!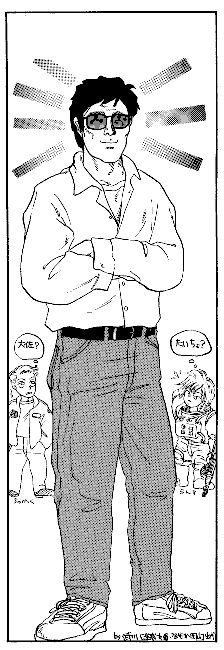
そんな日々、やたらに忙しい仕事の中の、ぽっかりあいた空白の時間に私は考えていた。
「俺は、ここで一体何をしているんだ」
「技術者の俺が、なんで苦情処理や、役所の面子
SF作家・谷甲州
SFらしきものを、初めて書いたのは高校生のころだったと思う。早い方ではない。作家の中には小学生のころから原稿用紙に向かっていたという人も多くいる。それから一〇年余り、ほとんど途切れることなくSFは書いていた。ただ好きだからという以外に理由はない。途中同人誌を作ったり、投稿したりもしたが、さっぱり日の目を見なかった。これもそんなに珍しいことではないだろう。
ところがネパールに渡って一年がたたぬ内に、それが珍しくなくなってしま
った。第二回奇想天外SF新人賞のせいだ。SF雑誌「奇想天外」の行ったこの賞の選考委員には、小松左京氏、星新一氏、筒井康隆氏という、すごい顔ぶれが並んでいた。
実はそれ以前に、日本にいたころ第一回の賞に応募したことがある。結果はさんたんたるものだった。第一次予選(応募総数の一〇分の一足らずが通過)にも残っていなかった。この時の佳作に選ばれたのがなんと一六歳の女の子だ
った。それだけでもがっくりしたが、選考委員の一人の「SFを書くのに人生経験なんて無い方がいいのかもしれないな」の言葉でさらにめげた。
彼女-新井素子さん-の“お話”が、もしつまらないものだったら、少しは気楽だったろう。事実は反対で、とにかく面白かった(白状するが今でも私は彼女の“かくれファン”なのだ)。面白すぎて呆然として、次に自分には才能がないことに気がついて、さらに呆然とした。
ここで傷心のうちにネパールに渡り、土方稼業に専念……ということになれ
ば大人なんだろうが、コリもせずに第二回の新人賞をめざしていた。そんな中
で“一三七機動旅団”を書き上げて送ったのが一九七八年の七月末ごろ、そろ
そろネパールでの生活に慣れてきたころだった。ところが、これも音沙汰がない。たぶん今度も駄目だったんだろうと考え、応募したことも忘れてしまったその年の暮れに、日本から一通の手紙が届いた。カトマンドゥJOCV事務所でそれを手にし、開封して手がふるえた。
「新人賞に佳作入選したので、受賞の言葉と略歴を送れ-奇想天外社」
あーとか、へーとか、うーとかいう言葉しか口から出てこず、誰もいない事
務所の二階をあっちうろうろ、こっちうろうろしてから別に用事のないことに
気がつき、下宿に帰ろうとしてバイクに乗ったがエンジンがかからず、何度キ
ックしても駄目で、強引に押しがけにしてもやっぱりかからず、相当引きずり
ましてからやっと気がついてキーを差し込み、夕暮れのカトマンドゥの街中を
無灯で走り抜けて下宿に帰りついた。
どうにもこうにも恥ずかしかった。それで、仲間にはかなりあとになるまでこのことは黙っていた。家族に至っては、二年後に最初の単行本『惑星CB-8越冬隊』が刊行された時まで、このことは発覚しなかった。
ところで、今でもよく聞かれるが、ネパールで生活していたことが原体験と
なって、SFを書いているのではないかという質問は、当時の私には当たって
いない。ネパールでの体験は後で述べるとしても、『惑星-』のころまではむしろ土木技術者として仕事をしていたことが、有力なバックボーンとなっていたようだ。つまり、技術者的な思考の訓練が架空の世界を構築する上で、非常に役立っていたような気がする。
例えば、小説の中に宇宙船が登場する時には、まず船籍を決め、建造された
状況を想定し、それにもとづいて規模計画を作成してから具体的な構造の設計
に入る。同時にソフト的な面、乗員の構成や、母港の機能も考えなければなら
ない。そういった面を整備しておいて、はじめてストーリーに入る。
ところが、最近になってそのような考え方に加えて、もうひとつの“原体験”が加わった。協力隊に参加したこと、およびその後の旅行だ。酒が時間をかけて発酵するように、じわじわとそれらの体験が書く上に影響を及ぼし始めたような気がする。
地球人、未来をみるか
未来史を作りたいと思っている。現在以降の未来を、未来史年表を作って下
敷きにし、歴史小説にして構築してしまうのだ。これは、SFでは昔から多く
作られていた。だが、本当に私が読者として満足できるものはなかった。ハイ
ンラインの未来史は、西部開拓史を宇宙を舞台に置き換えただけのような気が
する。アメリカ人は、建国以来、他人に価値観をひっくり返されたことがない。
十字軍のころから“悪いインデアンを懲らしめていた”時代を経て、ベトナム
戦争で泥沼にのめり込んでいった時まで、根本的に文明の枢軸側に彼等はいた。
地球人をさえ認識しきらない彼等に、宇宙を想像することができるのだろうか。
それなら、お前はできるのか、と聞かれると、自信は全くない、としか言えない。ただ、協力隊に参加したことで、“地球人感覚”を得ることができたと思っている。これを他人に理解してもらうのはむずかしい。要するに、最初に異なる文化の中に放り込まれた時、カルチャーショックにおそわれ、そしてその中にどっぷり浸かり込んで何年かたつ内に、突然相手の考えていることがわかるという、あの感覚だ。
話しが大きくなりすぎたが、要は西部劇の中の“ソルジャー・ブルー”を見
た時の感覚と、時代劇(歴史小説ではない)の中の“忍びの者”を見た時の感
覚を、私の未来史に書き込みたいと思っている。
あんまり大風呂敷を広げるのはやめよう。あとで引っ込みがつかんようにな
るから。
ヒマラヤの仲間
私は運命論者ではないが、偶然にネパールに行くことになって、そこで多く
の山仲間を得た。不思議なことだ。
協力隊の願書を出した時、山はやめるつもりだった。山を捨ててでも協力隊
員になりたかった。もちろん、測量隊員の派遣国にネパールがあることも知っ
ていたが「山が好きだからネパールに行かせてくれ」なんて、とても言えない。
派遣国の要請内容と、自分の経験が合えば、どこにでも行くつもりだった。不
合格になれば、また下水工事に逆もどりだから、何を犠牲にしてでも隊員にな
りたいという、切羽つまった気分だった。
そうは言っても、そう簡単に山をやめられる程度にしか登っていなかったわけではない。むしろ、願書を出した時には相当入れ込んでいて、正月はいつも南アルプスや八ヶ岳を縦走(ほとんど単独で)していたし、雪のなくなるころには岩壁や沢を登っていた。山を初めて一〇年余りになっていたが、このころになって本当に面白さがわかってきたようだ。
だいたいが、協力隊の二次試験前日まで山の中にいたのだ。朝一番で涸沢の
ベースキャンプを出て滝谷に入り、ルートを一本午前中に片付けてその日の内にベースを撤収して上高地へ下山し、夜行の汽車で東京に出て翌朝広尾で受験するなんてことをやっていた。派遣前訓練中にも、休日には山ばかり行っていたし、正月休暇には御獄山に登った。
だから、合格通知の電報を手にした時にはおどろいた。派遣国がネパールになっていたからだ。そうなると現金なもので、ネパール赴任時に発送した個人荷物の半分は書籍が占め、残りの大部分は山の道具だった。
それで、ネパールに渡ってからちゃんと山登りをしていたかというと、そう でもない。任期中は、かえってクライミング自体から遠ざかってしまった気さ
えする。ヒマラヤがでかすぎて、山旅行
そんな状態の、八〇年の春ころ、以前から知り合いだった日本ヒマラヤ協会
(HAJ)専務理事-と言えば聞こえはいいが、早い話がヒマラヤ乞食の典
型-である菊池氏から、カンチェンジュンガへ行かんか、という話を受けた。
翌年の任期終了後頃におこなわれる、HAJカンチェンジュンガ学術遠征隊の学術班のメンバーとして、登はん隊と共同しての同峰標高測量及び、周辺の氷
河の測量等を行うというものだった。
私はその場で、是非やりたい、と返答した。仕事自体にも興味があったし、
一般旅行者には解放されていないカンチ山域に入れることも、魅力だった。そ
して、一九八一年三月九日、三年一ヵ月にわたった任期の終了と同時に帰国し、
最優先の割り込みで隊員終了の手続きを終えて、その月の末にはネパールに取
って返した。その翌日に私は三〇歳になった。
登はん隊の連中は、みな若かった。そして、ギラギラと燃えていた。仕事や結婚なんぞ、どうでもいい、ひたすらヒマラヤだという猛者がゴロゴロいた。そしてみな気のいい連中だった。私には山仲間を得、そして後になって失うことをも知った遠征だった。
その遠征が終了してから、私はインドへ流れて行き、日本からの友達二人と
デリーで合流して、カシミール=ヒマラヤのクン峰(七〇七七m)をめざした。
速攻、というよりも力ずく、という感じで三人全員が登頂し、全員生還した。
カンチと違う面で私は多くのことを得、そして失った。
クンの遠征後、パキスタン北部のカラコルムあたりをうろついて、デリーに舞い戻ってきた時には一〇月に入っていた。ここで、カンチ遠征で知り合ったF氏の死を知った。その後のナンダ=カート遠征で雪崩にやられたらしい。そして、カトマンドゥに帰り着いた時、同じ仲間のK氏がアンナプルナ南壁で死んだニュースを聞いた。この年のヒマラヤはずいぶん人が死んだ。顔を知っている程度の人なら、他にもニュースを受けた。
山屋は、自分が死ぬ瞬間まで自分の死のことなど考えないものだ。そして、
友達の死を何回か経験していく内に、平然とそれを受け入れられるようになる
のかもしれない。私はまだそこまではいっていないが。
日本にようやくたどりついたのは、昨年の暮れのことだ。カトマンドゥで、
放ったらかしにしておいたJOCVの最終報告書を書いて、インド経由タンザ
ニアに飛び、キリマンジャロに登ったら金がなくなった。残金をかき集めてエ
ジプトに飛び、四〇〇〇年を見上げて日本へ直行した。これから、“彼等三人”がどこに行こうとしているのか、私にもわからない。その内にわかるだろう。

この文章は、青年海外協力隊の月刊広報誌『クロスロード』(『Closs Road』)昭和五七年六月号(第一八巻一九八号)に、『協力のなかの青 春③』というサブタイトルのもと掲載された文章を、谷甲州先生の許可を得て再録させていただいたものです。
なお、『クロスロード』では筆者名は本名でなされています。本誌では読者の便宜を鑑みて『谷 甲州』という形でさせていただきましたが、この文章の主旨からして、『SF作家 谷甲州』はこの文章の筆者の1/3に過ぎない、と考えるのが妥当であるかもしれません。