 |
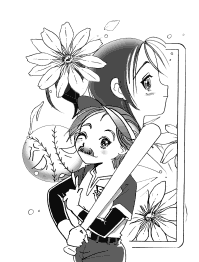 |
|
カットは売り上げが伸びるように、「Boys系」と「小さい女の子(または大っきい男の子)向け」の2点を用意しました。お好きな方のキャラで想像しつつお読み下さい。 |
|
そういうわけで、「日本沈没・第二部」の「読んだふり」をお届けする。もちろん「こうしゅうえいせい」読者のほとんどは特に読んだふりなどをする必要はないはずである。なんといっても、いま最もホットな甲州作品なわけなのだから。
今回のこの「読んだふり」は、しかし、それでもあえて──もう読んでしまったのにもかかわらず──読んだふりをしたい、そういう読者のために書かれたものである。今回は特に最初に書いておくが、この稿をもとにして「読んだふり」をした場合に発生するかも知れない不利益について著者は責任を持てない(いや毎回の「読んだふり」にしても責任なんて持ってないけどさ…)。
なお、第二部でないほうの「日本沈没」が未読の場合は、別稿の「読んだふりをするための『日本沈没』」を読まれるとよい──かも知れない。
 |
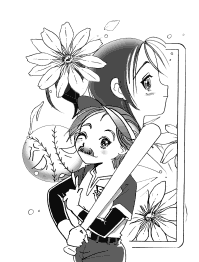 |
|
カットは売り上げが伸びるように、「Boys系」と「小さい女の子(または大っきい男の子)向け」の2点を用意しました。お好きな方のキャラで想像しつつお読み下さい。 |
|
日本列島が沈没して三十年が過ぎた。世界各国に逃れることができた日本人は、この三十年を…その宿主であるそれぞれの国の人々の顔色をうかがいつつ生きてきた。もともと「おれがおれが」という傾向が比較的少ない民族であったのだが、それがさらに強化されつつあるようであった。彼らの生活は決して楽なものではなかった──日本沈没の直前にはあれだけの経済的繁栄を経験していたのだから余計にそう感じられた──が、それでも各地の自治領──本当は特殊な状況を反映したもっとややこしい名前なのだが、多くの人はこう呼んでいた──はなんとか機能し、日本列島を脱出した七千万人とその子孫の多くは、それぞれの土地で、どうにかこうにか暮らしていた…。
米国内に設置されたままになっている日本国亡命政府──本当は亡命ではないし、もっとちゃんとした名前があるのだが、多くの人はいまだにこう呼んでいた──の首相として新たに選出された小泉純一郎は過激な言葉を好む性格であった。彼は次のようなモットーを掲げて周囲を驚かせた。
「日本をぶっつぶす!」
この発言を聞いたある閣僚は「…もうつぶれてるやんけ」とつぶやき、別の閣僚は「これからが勝負なのに」と眉をひそめた。もっとも、小泉純首相のこの過激な発言には彼なりの主張があった。
「待っていても日本列島が復活するわけじゃないし、どこかが領土を割譲してくれるわけでもない。日本民族としてはともかく、日本国民としてはそれぞれの国の中でそれぞれの国民として生きてゆくしかない。そのためには日本の…国としての歴史をいったん終わらせるしかない」
これに国土交通大臣──とはいっても国土がないのでほとんど名前だけの役職だが──が意義を唱えた。
「しかし沈没から三十年を経て、日本には…正確には日本のあった所には、人が住んでいます。彼らはあの場所での日本の復活を目指して活動しています。彼らが納得しないでしょう…」
「なけりゃ作ればいいじゃない、ほれほれ」
発端はそんな軽い言葉だったらしい。
日本列島はなくなってしまって、どうやら復活の見込みもなさそうだ。しかし、ないならないで新しく作ればいいじゃないか。それに…こういう活動は早くしないとどこぞの国が妙なことを考えたらややこしいことになる…。
彼らは、日本列島が沈没してから十数年が経過して地殻変動がいったん落ち着いたのを見はからって監視船団の隙をつき、かろうじて海面上に残っている、かつて日本アルプスの山々の山頂部であった島々の周辺に、浮体工法で日本の「国土」を作ってそこに住みはじめていた。当初は浮体による「国土」といっても大きめの浮き桟橋程度で、十数人程度の規模だったのが、話を聞きつけて船体や資材・機材とともにやってくる人間が増え、今では数千人規模の「都市」が誕生していた。日本国亡命政府は当初、危険を理由に退去を勧告していたが、今ではわずかながらではあるが東アジアの経済活動にも寄与しており、決して無視できない存在となりつつあった──。
彼らは自らを「日本.」(にっぽんどっと)と呼んでいた。彼らは少なくともいわゆる国としての「日本」ではないし、彼らの(浮体による)領土にしても人口にしても、かつての日本に比べれば点のようなものだ、というのがその由来だった。
「日本.」の中枢にはかつてのD計画の中心にいた中田や片岡がいた。彼らはもう還暦も過ぎていたが、まだまだアグレッシブで、「日本.」を国際社会に認めさせ「.」を取った「日本」とするべく活発に活動していた。
「なんかこう、まだ淡々としてるな、今のところ…」相変わらずのペースで働きながら中田はつぶやいた。彼はD計画のときと同様、この「日本.」プロジェクトの実施面での中心人物であった。
「そうはいっても…今のところは地道に領土──となる浮体──を増やしてゆくのが最善だろう。とにかく経済的に無視できない勢力になるのが第一、と言っていたのはおまえじゃないか」と片岡が言った。天才的なエンジニアと言われていた彼は、現在「国土」である浮体の基本設計から将来計画までを担当していた。彼が中心となって開発した高効率波力発電システムは、浮体による国土の維持に必要不可欠であるだけでなく「日本.」の主要な輸出商品の一つでもあった。
「なんていうか…こう、熱狂的な…古い言い方だと国威発揚的な…ものがあればいいんだが…」肩の凝りをほぐしつつあたりを見回して中田が言った。
「熱狂的っていうと、あれですかね。かつてあった阪神の応援みたいな奴…」誰かがなんとなくつぶやいた。
それを聞いた中田は動きを止め…一瞬の後に片岡に向かって言った。
「それだ、それ。おい、片岡、甲子園を作ろう。もちろんあの実物ほどのものじゃなくていいから、ちゃんとした野球場。それから野球チームも作ろう。名前も阪神タイガースでいい。『国民』のみんなが阪神ファンだったわけでも何でもないだろうが、賛否両論があるような熱気があるほうがいい」
小泉純首相は「日本をぶっつぶす」と言ったものの「日本.」をどうするかで悩んでいた。すでに数千人が住んでいて、経済的にもそれなりの実力を持ちつつある存在を無視するわけにはいかない。かといって、あれを認めてしまうと…国としての日本の歴史にいったん終止符を打つ、という彼の政策の実現は不可能になる。武力で──といっても、その場合は米軍頼みになるだろうが──どうにかするわけにもいかないだろう。国際世論も…少なくとも今のところはまだ…どちらかというと連中に同情的だ。
「やはりあそこを少なくともいったんは国連の直轄統治領にして、その上で国としての日本にいったん幕引きをする、というあたりかな。しかし連中がそれで納得するとは思えないし…」
「日本.」が野球場と野球チーム──なんと甲子園と阪神タイガースという名前らしい──を作った、というニュースが小泉純首相のもとに伝えられたのはその頃であった。感想を求められた首相はこう言った。
「しかしチーム一つでは試合ができんでしょう。紅白戦みたいなのばっかりやっててもねえ…」
「なんでも紅白の分け方が固定されていて、けっこう盛り上がっているみたいですよ。外国──といっても台湾あたり──からチームを呼んで試合をする計画もあるそうです」とそのニュースを持ってきた記者が答えた。
「我々…というか、あそこ以外の日本人でもチームを作ってあそこと試合でもしますかね…」と首相が何気なく応じたその時、件の記者が勢い込んで言った。
「それならいっそのこと、首相の例の『日本をぶっつぶす』をそれに絡めたらいかがですか。たしか先日も言われてましたよねえ、『日本をぶっつぶす』にはあそこに首相の政策を受け入れてもらうしかないけどなかなか…というようなこと。どうですか、向こうが阪神ならこっちは阪急にして『決戦!日本シリーズ』とか」
どうやらこの記者は、かんべむさしの「決戦!日本シリーズ」を読んでいたらしい。彼はあくまで冗談のつもりだったのだが、首相の反応は違った。
「そうだな…」彼はそうつぶやいてしばし沈黙した。そしてふたたび口を開くとこう言った。
「たしかに、意外とそれは名案かも知れない。このままだとなかなか効果的な手がなかったし、条件次第でなんとか連中にそういうのを認めさせれば乗ってくるかも知れない。いや、いいことを聞いた。ありがとう」
「え…ほんとにやります?ほんとにほんと?こいつはすごいや。記事にしてもいいですか?『決戦!日本.シリーズ』──見出しはこんな感じで…」
「あれを受けるのか?」片岡は中田に向かって言った。
「いいチャンスだ。これを逃がすとなかなかこういう機会はない。どっちにしてもこのままの…国なんだか経済地域なんだかよくわからない状態をあんまり長々と続けているわけにもいかないしな」
小泉純首相からの提案──というか挑戦状──は次のようなものだった。「『日本.』の阪神タイガースと、日本国政府が組織した阪急ブレーブスが野球の試合を行う。阪神が勝った場合は現在の『日本.』を正式な国家として認め、国名を『日本』とする。阪急が勝った場合は現在の『日本.』は国連の直轄統治領とし、国家としての独立は認めない。ただし、統治領の地域名称は『日本』とする」
「どっちにしても宙ぶらりんの状態から脱することができるし、一応、国かどうかはともかく我々は『日本』に住んでいることになる。それに…勝てば大願成就ってわけだ」
「しかし勝てるか? 向こうはきっと…何か考えてるぞ」
「こっちだって考えればいいさ…」
この試合における具体的な選手の構成や試合場所等に関しては小泉純首相からの提案に補足事項として書かれていた。「選手は日本人に限る。ここでいう日本人とは、日本列島沈没の時点で日本国籍を取得していた者かその子孫を指す。この件に関してはいわゆる帰化は認めない。試合会場および審判員は、第三国の関係者が望ましいという観点と地理的条件や設備面での条件を考慮して、米国本土の球場および米大リーグの審判員とする」
「第三国といっても、アメリカは…あきらかにあっちよりだよなあ。よし、せっかく甲子園を作ったんだから、試合場くらいはそこにしてもらおう。盛り上がるぞ…」
かくして決戦の日は来た。多くの関係者がある程度は予想していたが、日本国政府側・阪急ブレーブスには大リーグで活躍している選手が何人も含まれていた…。たしかに彼らは日本国籍を取得していた者の子供達である。これに対して「日本.」側・阪神タイガースは、基本的には本来のメンバーそのままで構成されていた。
決戦の場となった甲子園はもちろん超満員で、ほぼ全員が阪神の応援のためにやってきていたといっても過言ではない。「日本.」側に有利に働く点があるとすれば、この一点のみといってよいかも知れなかった──もっとも、元来の甲子園の十分の一、五千人程度の規模の観客ではあったが。
「しかし響くな…さすがだ」
試合を観戦に訪れていた中田が隣の片岡に声をかけた。
「応援人数が少ないぶん、音響効果にはかなり気を使ってるからな。今日の感じだと、グラウンドではかつての甲子園よりもすごい声援を受けている感じになるかも知れない」
「ま、どっちにころんでも、D計画以来延々とやってきた、長かった我々の仕事も基本的には終わるわけだ。今日は楽しませてもらおう」
そういって中田はビールを飲んだ。
試合は戦前の予想を覆す好ゲームとなった。阪急の選手が勝つことを厳命されていてやや緊張しているのに対し、阪神の選手は中田をはじめとする上層部から「ま、負けても仕方ないし」と言われてリラックスしているのが実力差を埋めたようだった。そして試合は阪急が1点リードで九回の裏を迎えた…。全世界に──といっても、主たる視聴者は旧日本の関係者だったが──放送されている中継のアナウンスにも熱が入る。なお、この放映権料も「日本.」の収入としてよいことが確認されていた。
「ノーアウト満塁の大チャンス。ここで…出ました、代打の神様、山羊です!初球を積極的にとらえて…これは犠牲フライには十分だ──三塁ランナー、タッチアップで帰ってきて同点!──いや、アウトです。アウト!信じられません、どういうことでしょう。あ、三塁のボブデー・ビッドソン塁審がランナーの離塁が早いと言ってます。そんなバカな。スローモーションで見てみましょう……どうみてもこれは誤審ですっ。しかし判定は覆りません、なんと一挙にツーアウト二塁一塁となってしまいました…」
「せこいマネしやがって…」中田はわめいた。「大リーグの選手を連れてくるとか、審判員が若干あっち寄りだとか、そんなくらいは想像していたが…。ここまであからさまなことをしてくるとは思わなかったぞ。くそう、小泉純の奴…」
そこで場内アナウンスがまたしても代打を告げた。「代打、ハスミ…」
アナウンサーがハスミの資料をめくりつつ実況をつづける。
「ここで代打・ハスミの登場です。何でも、阪神が今回のために特にスカウトした選手だそうです。祖父は旧帝国海軍の戦闘機乗り、父は旧航空自衛隊のパイロットで、本人も米国空軍の現役のパイロットだそうです」
ハスミはゆっくりと打席まで歩くと小さくつぶやいた。
「よかった。俺の出番があった…」
かくして「決戦!日本.シリーズ」は嘘のようなハスミの代打逆転サヨナラホームランで阪神の勝利に終わり、かつて日本列島があった場所に国家としての日本が復活することになった。これに関しては政治形態その他に関して小泉純と中田の間の激しい応酬も見られたりしたのだが、それはまた別の話である──。
思っていたよりかなり長くなってしまった。これもきっと第二部の壮大さ故かと思う。新生日本に関する第三部が書かれるという話はいまのところはなさそうである。今回のあらすじでは触れなかったが、作中には第一部の重要人物である小野寺も当然登場する。潜水のプロである彼が浮体工法による国土実現の一端を担っていたのは言うまでもない。
なお、今回のこの稿は筆者のポルトガル滞在中の六月八日・九日に書かれているため、執筆の時期と場所に関する様々な影響を受けている。冒頭にも書いたが「読んだふり」をされる際にはこのあたりについてもいろいろと考慮されることを希望する。