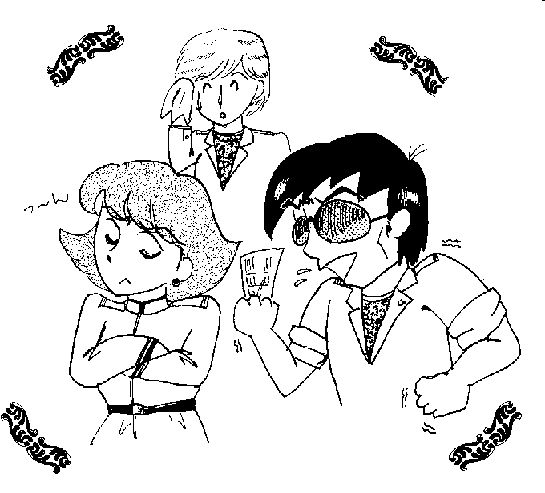
……タナトス・コマンド中隊、通称タナトス戦闘団に実は女性隊員がいたことは知られていない。終戦時にカリスト軍がタナトス戦闘団に関する資料を破棄してしまったこと、彼女が実戦にはほとんど参加しなかったことなどが原因である。しかし、この一種独特の気風を持った中隊の中にあって、当時彼女の存在があらゆる意味で異彩を放っていたことは確かであった。
カロライン・佐山少尉が入っていった時、オフィスにいたのはランスこと副隊長のローレンス・ブライアント少佐だけだった。何やら黙々と端末に打ち込んでいる彼に、佐山は問いかける。
「フェルナンデス少佐は……隊長はどちらに?」
「さあね」
「また雲隠れですか」
ランスの答えに、まだ若い女性少尉は形式的に眉をひそめたが、それも一瞬のことだった。手にしていた書類を彼に差し出す。
「ブライアント少佐のほうが好都合です、隊長じゃ話にならないから……これを見ていただけますか?」
「?」
「タナトス戦闘団の補給、修理申請一覧です」
佐山の手から、ランスは書類を取った。一瞥して不思議そうに彼女を見やる。
「これがどうしたんだ、承認は済んだんだろう?」
「副隊長はこれ、チェックされました?」
「もちろん」
「なにか気付きませんか?」
そう言う彼女の声は、不自然なまでにおだやかだった。背中に冷たいものを感じながらもランスは首をふる。
「……なにか不審な点でもあったか?」
「大ありです!」
突然、佐山の声が高くなった。
「どうしてこういつもいつもいつもいつも、訓練の度に莫大な申請が出るんですか! 実戦してるんじゃあるまいし、一体どういう装備の使い方をなさってるんです」
「……それは隊長に言ってくれないか。計画をたててるのは隊長なんだから」
「言いました! 何回も!」
逃げるようなランスの言葉だったが、それは彼女の怒りに火を注いだだけだった。3つも階級が上の上官の鼻先に、佐山は指をびしりとつきつける。
「毎回私がどんな苦労をしてデータを処理してるかわかってるんですか? 経理担当をするほうの身にもなってください! もうちょっと節約しようとか大事にしようとか、そういう考えはないんですか?」
「…………」
……カリスト防衛軍には、公式にはタナトス戦闘団などと呼ばれる組織は存在しないことになっている。新設されたのは、あくまでも国境警備隊に所属する特殊装備部隊としての陸戦隊だった。最近増えてきた港湾施設での凶悪犯罪に対抗するためというふれこみだったから(ついこの間も、麻薬中毒患者がアルテミス宙港で銃の乱射事件を起こしたばかりである!)規模もそれなりに小さく、従って組まれた予算も微々たるものであった。
しかし、実際のタナトス戦闘団はれっきとした戦闘部隊である。とてもではないが警備隊の一部門あたりに配られるような予算では、運営できる代物ではない。そこで一策として、予算と実際にかかってくる金額の差額を、不自然でない形で他の経理データにまぎれこませる処理が行われているのである。
そして、その作業の責任者がカロライン・佐山少尉だった。警備隊の統括者である山下准将と同じ日系の佐山は、年齢に似合わぬ高い事務処理能力と、情報操作の才能を持っていた。そこを見込まれて、これまでいた財務部から引き抜かれてはきたのだが……ここでの仕事は、いささか彼女には我慢しがたいものだったようである。
「しかし少尉」
佐山の勢いにやや閉口しながら、ランスは抗弁を試みた。
「いちいち節約なんか考えてたら訓練できないだろう。うちはまだ編成も戦術も試行錯誤の段階だ。損失が多少大きくなるのは仕方ないじゃないか」
「少佐……」
佐山は明らかに我慢する表情になる。彼に怒りをぶつけても仕方ないことを悟ったのだろう。
「そのくらい分かってます。私が問題にしてるのは『大きい』ことじゃありません。『大きすぎる』ことなんです」
「というと?」
「このままだと絶対、データがどこかおかしいということが知れますよ。もしそれが航空宇宙軍の耳にでも入って、彼らが本気で調べでもしたらどうするんです?」
「それをさせないようにするのが君の仕事だろう」
「ものには限度ってものがあります!」
彼の台詞に彼女は再び爆発した。両手でデスクを叩いたはずみに身体がわずかに跳ね上がる。
「装備は宇宙から降ってくるもんじゃないんですよ。使えばそれだけお金がかかるんです。それをもうちょっと考えろと、私はそう言ってるんです! 原因はそっちにあるのに私になんとかしろとは何事ですか!」
「わ、わかった……わかった」
半分逃げ腰になりながら、なだめるようにランスは応じる。
「隊長には良く言っとくから」
「言っとくだけじゃありません。実行させてください」
「わかった、なんとかやってみるよ」
「やってみるんじゃなくて、やるんです」
「少尉……」
「今度こんなべらぼうな申請が出てきたら、容赦しませんよ」
「…………」
彼女は本気だ、とランスは思った。一体どんな「容赦のないこと」をされるかは知らないが、絶対ろくでもないことに決まっている。なんとかアイディアはないものかと彼は思案し、そして絶好のいいわけを見つけた。
「しかしな、少尉」
ランスはため息をつき、深刻な顔で腕を組んでみせた。
「あのダンテ隊長に、そんな器用なことできると君は思うか?」
「そのために副隊長がいるんでしょ、ブライアント少佐」
……だが、真顔で佐山はそう言ってのけたのだった。
「なに言ってやがる」
ダンテ隊長ことヘロム・フェルナンデス少佐は、ランスが予想したとおりふんと鼻を鳴らした。
「そんな偉そうなことぬかすんなら、もっとましな装備をよこせってんだ。事務屋が後ろからごちゃごちゃ言うんじゃねえや」
ひと嵐起こしたカロライン・佐山が去ってからしばらくして、一体どこへ行っていたのかふらりとダンテがオフィスへ姿を現した。そしてランスから一部始終を聞いた後、言った台詞がこれである。
「しかし、あの分だと山下准将まで行くかもしれんぞ、少尉は」
「それがどうした。こっちは准将直々の命令で陸戦隊やってるんだぞ」
「佐山少尉も准将が直々にひっぱってきたんじゃなかったかな」
ランスの指摘に、ダンテはいやな顔をした。それでもしばらくなにか考えたようだったが、やがてぐいと肩をいからせる。
「……とにかく、そんな話は聞く耳持たん。今度ねじこんできやがったら、少尉にはそう言っとけ」
今度はランスがいやな顔をした。
「隊長が直接言ってくれよ。あの少尉は苦手だ」
「お前の方がここにいることが多いじゃないか」
しれっとして言い放つダンテに、そうさせてるのは誰だと応じかけてランスは黙りこんだ。何となく、ダンテと佐山少尉が直接対決したら、自分がいちばんとばっちりをくらいそうな気がしたからである。
「……また行ったんすか、隊長のところに」
椅子にふんぞりかえったまま呆れたように佐山に言ったのは、エミリオ・ロドリゲス軍曹、通称ロッドだった。
「無駄だって言ってるのに……」
「猿だって5回も練習させれば、芸を覚えるのよ」
「隊長は猿以下ですかい」
ロッドのぼやきにも答えず、佐山は不機嫌な顔で端末の画面をスクロールしていた。システム面から彼女のサポートをしているロッドは、やれやれと肩をすくめる。士官学校出の彼女より階級こそ下だがキャリアはずっと長いロッドにとって、佐山の態度はまるで子供に見えるのだった。
それでもなだめるように、彼は言った。
「まあ、あの人に言って聞かせようってほうが無理ですよ、少尉。なにしろああいう人ですからね。経費が自分の給料からさっぴかれるとかいうんでもない限り、真剣には……」
不意に佐山が振り返ったので、ロッドはびっくりして口を閉じる。
「それいいアイディアね!」
「はあ?」
「そのお給料って話よ!」
彼女の眼は輝いていた。それを見たロッドはなんとなく不安になった。
「……給料がどうかしたんですかい?」
「自分のお給料からさっぴかれない限りって言ったでしょう、軍曹」
「……そういえば言いましたね」
自分の予感が当たってないことを祈りながら、彼はもごもごと答える。だが、次に佐山が言ったのはまさしく予感通りの言葉だった。
「フェルナンデス少佐に、お金と物資のありがたみをいやというほど叩きこんでやるわ。軍曹、ちょっと手伝ってくれる? ネットワークをいじりたいのよ。あなたのことは黙っててあげるから」
「…………」
ものすごくうれしそうな顔でキーボードに指を走らせる佐山を見て、自分はもしかするととんでもないことを言ってしまったのではないかとロッドは思い悩んだのだった。
そして、給料日のことである。
自分の給与明細に眼を通したダンテは、文字どおりひっくり返った。
「な、なんだこりゃあ?!」
「どうした?」
叫びを聞いて不審に思ったランスが声をかける。その彼の鼻先へ、ダンテは明細をつきだした。寄り目でそれを眺めたランスは思わず吹き出した。
「……いつの間にこんなに借金作ったんだ、隊長」
「俺は知らん!」
ダンテは吠えた。
「全然身に覚えがないぞ! 経理コンピュータが壊れてやがるんだ!」
「経理コンピュータが壊れる可能性よりは、隊長が実際に借金をした可能性のほうが高いんじゃないか」
「俺は知らんと言ってるだろう!」
ダンテは給与明細を叩きつける。だが薄い紙切れにすぎないそれは、小馬鹿にしたようにひらりと床に舞い落ちただけだった。余計腹を立てたダンテは明細を踏みにじろうとしたが、ランスが危うく押しとどめ、拾い上げると子細に眺めた。
特に金銭に関わる経理コンピュータは、保守も桁違いに厳重である。ランスの言葉どおり、その経理コンピュータに狂いが生じたというよりは、ダンテが自分の借金を忘れている、という可能性の方が高いのだ。もっとも、この万事に対しておおざっぱなダンテが、借金をするというのもこれまた妙な気はするのである。金などあってもなくても気にしない、というのが彼のライフスタイルであるからだ。
給与明細には借金の内訳は書かれない。単に「一般貸付」という項目にトータル金額が打ち出されるだけである。だがその金額に見覚えがあるような気がして、ふとランスは眉をひそめた。しばらく考えてようやく思い出す。
「……補給申請書だ!」
「なんだって?」
部屋の中を歩き回っていたダンテが足を止めた。
「こないだ佐山少尉が文句を言ってきた申請の金額と、借金の金額が同じなんだよ」
「……あの女!」
それ以上、ダンテは聞かなかった。歯ぎしりすると猛烈な勢いで部屋から飛び出していく。あわててランスも後を追った。
「……あらおはようございます、フェルナンデス少佐、ブライアント少佐」
オフィスでファッション雑誌を読んでいた佐山少尉は、血相を変えてとびこんできたダンテとランスを眼にして会釈をした。そんな彼女の前にダンテはつかつかと歩み寄り、胸ぐらをつかみあげようとして……さすがに遠慮したか手をおろすとぐいとにらみつける。
「俺の給料になんの細工をした」
情けない台詞だったが、本人にそのことを自覚する余裕はなかった。佐山は雑誌を広げたまま、ダンテを見上げた。
「意外と早くわかったんですね」
「営倉にぶちこんでやるからそう思え」
「そんなことすると、少佐の借金は永久に消えませんよ」
「……うっ」
彼女の言葉に思わずダンテはひるむ。その隙をついて、ランスが割り込んだ。
「少尉、これは営倉どころか軍法会議ものだぞ。経理コンピュータにハッキングするなんて一体どういうつもりだ」
「そんな危ないことしてません」
やや憤然としたように佐山が言い返す。
「軍委託のローン会社の回線に入って、経理あてのデータを流しただけです。経理コンピュータはなんの問題もなく受理しているはずですよ」
「……なるほど」
「感心してるんじゃない、ランス!」
ダンテがわめいた。
「いいか少尉、すぐに俺の給料をもとに戻せ。さもないとエアロックから叩き出すぞ!」
「今後無茶な補給申請を出してこないって約束するなら、なんとかします」
「そんな約束できるか! 戦争をなんだと思ってやがる!」
「じゃあ、当分返済に苦しんでください」
「……ううっ」
「少尉、俺からも頼む」
見かねたランスが再び口をはさんだ。
「隊長にはこれから気をつけさせるから」
佐山は眉をあげ、ちらりとランスに眼を向けた。
「本当ですか?」
「約束する」
自分がとんでもない厄介ごとを抱え込む羽目になるのはわかっていたが、放っておけばこのままふたりは果てしなくエスカレートしていきそうだった。ダンテの危険な視線を感じながら、ランスはうなずく。
佐山はにこりと笑った。
「分かりましたブライアント少佐。それではお願いしますね」
ダンテは射殺しそうな勢いで佐山をにらんだ。だが結局なにも言えず、ランスになだめられる形でオフィスを後にするほかなかった。
ダンテ隊長、佐山少尉に敗北、といううわさがその後タナトス戦闘団内を伝わったのは、あっという間のことである。だが、その件に関して触れるものは余りいなかった。なぜならば、うっかり口にしようものならばダンテの機嫌がものすごく悪くなるからである。そして、機嫌の悪いダンテがどんなに厄介なものか、皆骨身にしみて知っているからだった。
……このあと数日に渡って行われた「特別訓練」によって……。