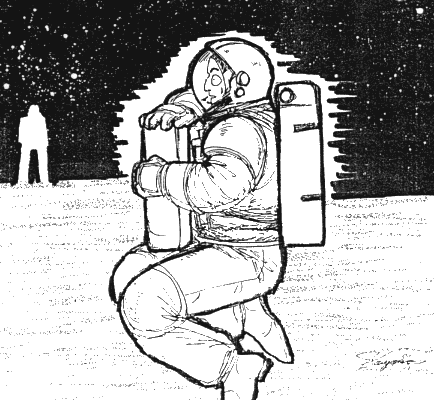 |
外惑星と言えばいまだに過酷な自然環境を連想する人が多い。あたかも二十世紀の東京・大阪の人が北海道を世界の果てと思っていたのと合い通じるものがあるかもしれない。
『アレクセイにとってそれは信じられないような事故であった。カリストの都市の間を弾道飛行しているときに宇宙船の機関が停止してしまったのだ。こんな単純な宇宙船に故障なんかありえない、だが現実は彼の目の前の残骸が教えてくれる。
都市の管制センターは幸いにもおおよその位置は把握してくれたらしい。しかし、ここまで救援隊が来るには最低でも12時間は必要なはずであった。地形が悪くとても宇宙船が直接着陸できる状態ではないからである。
こんな場合には死んだ同僚と生き残った自分のどちらが好運なのだろうかとアレクセイは思った。彼の手持ちの酸素は持ってもあと8時間分しか無かった。しかも足をどうにかしたらしく歩くことは不可能だった。
それでも自殺しなかったと言う事は彼は生き残った事をやはり好運だと思っているのだろう。
文字どおり座して死を待つ状態が6時間以上も続いただろうか。遠く岩陰から何か近付いてくる。夜のカリストでそんな物が見える訳はないのだがしかしアレクセイには何かがこちらに近付いているのが解った。
どうやらそれ自体が何等かの光を放っているらしいソレはやがて人の形を取り始めた。それが本当に人間だとしたらずいぶんと遅い歩みであった。それは低重力に慣れていない人間の歩きかただった。
「ここだ!」無線機は故障し、酸素の残りが乏しい事も忘れてアレクセイは絶唱しさかんに手を振った。
その人はアレクセイを認めたようだった。近付くにつれてアレクセイはその宇宙服がカリストの物ではない事に気がついた。ヘルメットの光に照らされたその宇宙服は随分と疲れた感じではあったが明かにあの例の航空宇宙軍の戦闘用宇宙服であった。しかも肩に見える記章は陸戦隊の所属であることを示していた。
アレクセイは青ざめた。事故とは言え自分は事もあろうに航空宇宙軍陸戦隊の秘密演習場かなにかに墜落したらしい。SPAの親派かスパイとでも思われたら彼の将来に希望はない。自殺と言う考えがアレクセイの脳裏に初めて浮かんだ。
だが意外な事にその人はアレクセイの酸素が残り少ない事を認めたのか手持ちの予備酸素ボンベをアレクセイのバックパックに装着するとそのまま歩みさってしまった。そのとき初めてアレクセイはその人が武器を持っていない事に気がついた。
来たときとは反対の方向にその人はただひたすら歩いていた。その人の姿が見え無くなって数時間後に救援隊が到着した。彼らはアレクセイを助けた謎の人物を宇宙船からも地上でも目撃しなかった。
アレクセイの懸命な調査の結果、外惑星動乱当時に陸戦隊が臨時に編成されたらしい事は解った。公式記録にはカリストにそれらが投入された事実は全くなかった。それでもアレクセイの手元には航空宇宙軍の予備酸素ボンベが残っていた。陸戦隊の記章をつけて。』
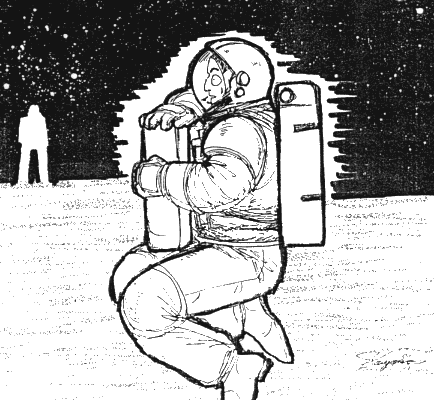 |
外惑星の歴史を考えるときあの外惑星動乱の意味は大きい。それはたった一年程度の戦争であったにもかかわらず都市伝説の多くが何等かの形で影響を受けていることからもわかる。
そんな中でこの話はきわめて特殊な傾向をもった伝説である。なにが特殊であるかというとこの話は実は出典を地球に、それもアジアにまでさかのぼれるのである。
インド亜大陸と言うと外惑星領域に住む人間にとっては隣の恒星よりも未知の領域であろう。ほとんどの人間はその存在も知らないだろうし、ごく一部の限られた人間にしても「甲州が低く飛ぶ日は天気が悪い」と言う言い伝え以上の知識は無いはずである。
この我らにとって未知の領域であるインドにはヨガの行者と言うなんらかの宗教に結び付いた職業があったと言われる。彼らには瞬間的に惑星表面を移動する事が可能であったと言われている。(なお学会ではヨガの行者とは民衆が科学者を理解するために作り上げた言葉と言う説を支持する専門家が多い。じっさい核エネルギーなどの分野でインドは非常に高い水準にあった。それを実用化するのを阻んだのが身分制度などの社会的な矛盾のせいだとされている)
砂漠を移動する遊牧民などは荒野を風のように過ぎ去るヨガの行者の幻を見ることまれではなかったと伝えられている。その話の中には今回のように砂漠の遭難者を助けるのも当然ある。
さて、この話の出典が解ったところで一つの疑問が生じるだろう。ヨガどころかインドすら知らない人間が多い外惑星においてどうしてこの話が生まれたのか。
この謎を解く鍵は航空宇宙軍陸戦隊と言う部隊にある。軍の組織に少しでもくわしい人なら外惑星動乱当時、航空宇宙軍に陸戦隊など存在していなかった(少なくとも公式記録では)事を指摘できるだろう。
ところで外惑星動乱終結とともに都市部は航空宇宙軍治安警察部隊の軍政下におかれていたが、この治安警察軍の宇宙服はこの話に出てくる陸戦隊の装備と非常に酷似している。
そしてこの治安警察軍の第一陣は都市部でのテロ活動に備え構成員の多くがインドのいわゆるグルカ兵出身から選ばれたと言う。都市でのテロ活動も無かったためこのグルカ兵たちは逐次、別の非グルカ兵の治安警察軍と交替させられた。つまり彼らは第二陣の軍の楯として扱われた事になる。
テロ活動は無かったものの外惑星諸都市の市民の視線が占領軍に対して温かいものだとは思えない。しかし、常に危険な任務に投入されるこのグルカ兵の一団にとって心の支えはなんだったのだろう。それは支配者としての自分達だったのだろうか? 本当は人命を救うための組織である航空宇宙軍の一員である誇りだろうか。