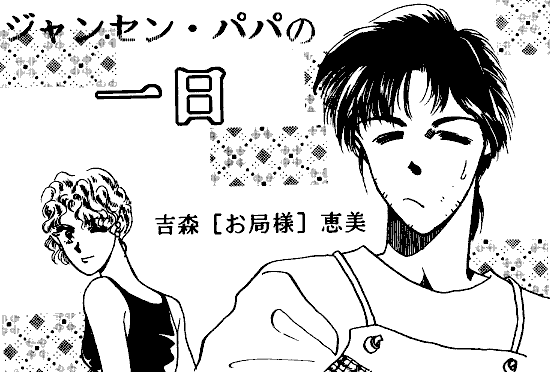
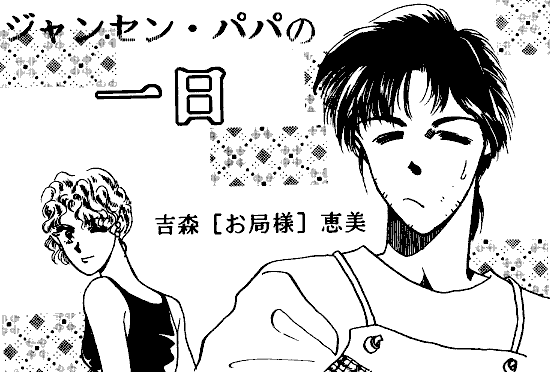
−ミセス・ジャンセンは御主人の貴女の仕事に対する御理解についてどうお考えですか?−
−とても言葉では言い尽くせませんわ。私の仕事を誰よりも理解してくれていますし・・・よく小説家だったらモチーフに苦労せずに済んだろうに、なんて言ってますけれど−
−まぁ。御主人は確か有名なイラストレーター・・・・−
ぶちっ
「パパぁ、ママがでてるのに切らないで」
「そうよ。だいたいねぇ、パパってばシャイすぎるわよ。ママのインタビューくらい照れずにみれないの?」
「うるさい。とっとと飯食って出ないと、遅刻するぞ」
どうせビデオは回してあるのに、未練たっぷりに画面を見やり、それから壁の時計に目がいく。子供2人は目を丸くしオレンジジュースでトーストを流し込む。大体、最近生意気な口をききすぎる。
「ママはまだ起きないの?」
下の子がぐずぐすと支度しながら・・・・どうやら彼女が起きてこないかとかすかな希望を抱いていたらしい。だが、深夜に帰宅し、眠ったのは明け方。いくらパイロットが頑強な体力をもっていようが起きだすのは無理だろう。
「だめだめ。さっさと出ないとスクールバスがいっちまうぞ」
「はぁぃ。いってきます。パパ」
「いってきまぁす」
2人の子供は軽いキスを残し、勢いよくフロリダの太陽の下に飛出していった。
再びテレビをつけるとにこやかな笑顔のインタビュアーの隣で妻が笑いかけている。少し緊張した顔。
−働く女性シリーズ。本日は宇宙空間を舞台に活躍されいている、NASAのスペースパイロット、ミセス・レベッカ・ジャンセンを お迎えしました−
「いいワンピースでしょ」
以外と元気そうな声が背後から投げかけられる。バイロットの体力は桁外れだ。感心していると自分でコーヒーを入れカウチに腰掛ける。
「この間、トーキョーで買ったの。あら、あの子達学校行っちゃったのね」
ぐるりと室内を見回して、眉をひそめて考え込む。随分してから室内の違和感のモトに気がついたのだろう、表情が明るくなる。重々しい口調で断言する。もっとも当たった例はないのだが、女としてのプライドが許さないのだろう。
「ソファーを買い替えたのね?」
「外れ。カーテンをかけかえた。ソファはカバーを替えただけ。あとは配置を少しいじった」
「・・・・・ふぅん。いいんじゃない」
レベッカはコーヒーを飲み干すと渋々感想を言う。
「さぁて、もう一回眠れそうね。12時に起こして、美容院にいくから」
軽いキスの代償はぬくもりの残る、NASAのロゴ入りマグカップだった。
洗い物を食器洗い機に放り込み、洗濯機を動かしている間に寝室以外の部屋に掃除機をかけていく。
小一時間ほど家事をこなし自分の時間がやってくる。
家事も子育てもさほど苦になる訳ではない、時間に囚われない自由業。シンと静まった家の中で裏庭に面したアトリエへと入っていく。描き散らかしたイラストが創造主を迎える。
創造主は行き詰ったまま、窓から見える隣の庭に植えられたパームツリーの葉の数を数えていた。それから今夜のパーティーのメニューと手順。メインディシュはローストビーフ、ワインはとっておきのを寝かせてある。ワインといえばレベッカと出会ったのは、あるパーテ
ィーで彼女の一張羅の白いドレスに赤ワインをぶちまけたからだった
っけ・・・・。あのあと宇宙飛行士だと聞かされて驚いたもんだ・・・。何しろ宇宙飛行士ったら今でもエリート中のエリートだものな。
よし、ワインはあの時のブランドにしよう。
一年の半分は訓練や研修、残りの半分は宇宙の上、その半分が・・・。ま、定年まで宇宙に上がりつづける訳でもないだろうし、そのための事故の確率など交通事故以下とわかっていても、たとえば1986年の事故のフィルムを見ると寒気が走ってしまう。もし、と。
子供達にとってはいちばん自慢の母親であるレベッカ。本当に小さな頃には『ママにあいたいよぅ』と寝ぼけ眼で泣きつづけた子供達。だが、中継される映像に誇らしげに映る彼女と、実体をもって家の中にいる彼女とどこまで区別がついていたやら・・・。
セットしておいたタイマーが時間を知らせる。
今日の夜はここで親しい友人達を呼んで、ちいさなパーティーを開くことになっている。その支度をはじめないといけない。
手始めはレベッカを起こして美容院に行かせる。その間に料理の下ごしらえとリビングのセット。
創造主はアトリエを後にした。
「レベッカ、12時だよ」
厚いカーテンが窓際からの外光の侵入を許さずにいる。
薄暗い寝室のベットには朧気な輪郭が浮き出ている。
「サシミ・・・・スキヤキ・・・スシ・・・・」
「はぁ?」
やはり宇宙空間なんてのは、脳味噌に変化を起こさせるのだろうか。
ベッドの端で真剣に悩んでいるとまだ眠り足りないらしいレベッカが寝返りをうち、その動作で目を覚ます。
「もう時間? いやだわ。とってもおいしい日本料理のフルコースをアキヤマとハスミ社長に奢ってもらうとこだったのに・・・・」
「レベッカ・・・君ね」
うっとりとしたレベッカの視線に、嫌な予感が走り抜ける。
「そうだわ!今日のメニューは日本食にしましょう」
「何を言ってるんだ。材料だって買いこんであるし、僕は日本料理なんて出来ないよ」
「大丈夫よ。私が作るわ。ほら、ハスミ社長の奥さまは料理の天才ですもの」
いそいそとこのアイディアを実行に移すべく起きだそうとする彼女の活動をどう阻止するか考えながら、頭をフル回転させはじめる。
「心配?」
もちろんだ、と心の中できっちり断言してから、どう意志表示するかが問題だ。別に彼女の料理が下手だとか、家事に関してとてつもなく不器用だという訳でもないのだが、本人が思っている以上に適性外なんだがなぁ・・・・。
「レベッカ。いいかい、今日のローストビーフの材料はだね、日系デパートのショップから取り寄せたコウベウシのシモフリでとっても高かったんだ。君のために家計をやりくりして手に入れたんだ」
「まぁ!シモフリというのはスキヤキやシャブシャブに一番あうんですってよ」
「誰がそんなことを・・・」
「ハスミ社長の奥さま」
「だけどね・・・・」
「だめ?」
するりと肩に両腕を回され、まるきり子供のような表情で問いかけられると、嫌とはいえない悲しさよ・・・。天井に向かってため息を吐き出す。
「わかった・・・美容院にいってきたら?」
「愛してるわ」
両手を挙げて降参ポーズをとると、嬉しそうに抱き付いてくる。
確かこの間雑誌に日本料理の特集が組んであったな。探し出して、足りない調味料を揃えないと・・・ああ、頭いたい。
『まぁ、それは大変ねぇ』
電話の向こうでおかしくて仕方ないといった様子で笑うのは、日本から赴任してきた企業戦士夫人で、カルチャーセンターで茶道に華道を教えている。急遽変更したメニューの相談中である。
『いいわ、調味料と細々したものは貸してあげるから、取りにいらっしゃい。レシピも書き出しておくわ』
「ありかとう」
『いいのよ。その代わり、今度御自慢のローストビーフ、ご馳走してね。それにしても奥さん思いなのねぇ。うちの亭主に爪の垢でも飲ませてやりたいわ』
結局それから、その夫人宅に行って段ボール一杯の材料とレシピを受け取り、材料と格闘する破目となった。
「ただいまぁ!パパ何してるの?」
「おおッ。いいとこに・・・・これをかき混ぜるんだッ」
「ママは?」
「美容院。帰ってくるまでに仕上げるぞ」
学校から帰ってきた子供を巻き込んで、料理の下ごしらえにてんてこ舞いしているうちに時間は過ぎていった。
料理の支度が出来上がるのと、ドレスアップしたレベッカが帰宅したのはほとんど同時で、客がやってくるまでもあと少しだ。子供達にシャワーを使わせ、いちばんいい服を着せる。もちろん、自分もとっておきのタキシードに着替える。
「結婚記念日、おめでとう」
ほっと一息つく間もなく客達が手に花束やら、ワインを片手に集ま
ってくる。
「ありがとう。今日は趣向を変えてみたんだ。楽しんでいってくれ」
「まぁ、楽しみだこと」
料理は好評で、特に苦労して手に入れた肉が化けたスキヤキ・シチューは絶品の評価を受けた。
客が帰り、子供達が寝入った頃もう一度、奇麗にルージュをひきなおしたレベッカがテラスへ誘う。
それぞれがシャンペンのグラスとボトルとオードブルを抱えている姿は笑えるが、いたずらっ子の様に笑う彼女はとてもきれいで、こちらまでにんまりしてしまう。
「怒った?」
「どうして?」
「あなたの御自慢料理を変更させたから」
「おかげで、レパートリーが増えた。主夫業は僕の天職かも」
「まぁ、私あなたの絵が一番好きだわ。インテリアのセンスもいいし」
「僕も君が一番好き」
片手にはとっておきのシャンパン、片手にはレベッカ。身体を寄せ合い他愛もない事を囁き合う。
明るい月の光が二人を照らし、地上に降りた天使、ならぬスペースパイロットとしがないイラストレーターは宇宙に乾杯を捧げる。
幾度めかの結婚記念日の夜の事である。
END