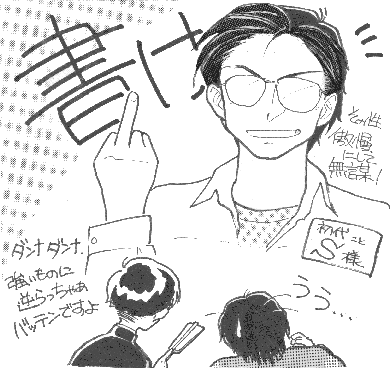
去年の『こうしゅうえいせい力技』で、『星界の紋章・増長日記』なる駄文を書かせてもらった。その末尾には「来年は『凋落日記』をお届けできると思う」と記したはずである。
だが、この言は撤回せざるをえない。なぜなら、わたしはいまだに増長の真っ直中にいるからである。ああ、選ばれし者の恍惚と不安、我にあり。
それでは『新・増長日記』をお届けするべきなのだろうか。
やろうと思えばネタはいくつもある。去年の『増長日記』では締切の関係で、「思ったよりたくさん本が売れました」というバカみたいなことしか書けなかったのであるが、その後、ファンレターもたくさんもらったし、ファンジンも何冊か出たし、インターネットにサイトができたし、ガレージ・キットも出たし、といろいろ嬉しいことがあったのだ。
しかし、やらない。理由はふたつある。
他人の自慢話を二年もつづけて読みたがる人間が果たしているのだろうか、という根元的な疑問が理由のひとつ。もうひとつは、どうせ自慢するのならあの件についても自慢したいのだが、あなたがこの文を読んでいるこの時点で、どこまで明かしていいのやら見当もつかないのだ。『星界の紋章』はもうわたしひとりのものではないらしい。適当に察してもらいたい。ああ、いいたいよう。
だが、浮かれてばかりもいられない。光があれば闇がある。
『星界の紋章』はヒットした。『脳○革命』の前ではベストセラーなどと呼ぶのははばかられるし、三巻まとめても『グ○ン・サーガ』の一巻にもかなわないていどのヒットだが、まあ、そこそこ売れたのだ。
すると、金の匂いにひかれてハイエナがやってくる。世の中、そういうものだ。
(筆者註:この物語はフィクションであり、実在する人物・団体とはいっさい関わりがありません……と表明しろという圧力がかかったので、しぶしぶ関係ないことにさせていただきます)
「同人誌つくって、コミケに出しませんか?」
実在の人物とはまったく関係がないということにやむを得ずするのだが、初代隊長S氏がいった。
「同人誌って、なにの?」
「もちろん、『星界の紋章』の」
「はあ……?」
わたしは首をかしげた。いろいろ事情があって、プロの漫画家や小説家がコミケに出店する例は知っている。だが、いまのところ、わたしには非商業ベースで作品を発表しなくてはいけない理由などない。それより、この人生にたった一度きりかもしれないビッグ・ウェーヴを捕まえるので精一杯、とてもファンジンまでは手がまわらない。だいたいなにが悲しゅうて、自作についてのファンジンをつくらにゃならんのだ。
その理由を問いただすと、表向き実在の人物とはまったく関係のないS氏は「金儲けである」と明快にこたえた。
つまりわたしが小説を書く。香月隊員にイラストを描いてもらう。これをコピー誌にする。原価はせいぜい百円ぐらいのものだろう。どこかのコピー機が利用できれば、限りなく只に近づく。このぺらぺらのコピー誌を「作者が一冊一冊、念を入れています」と称して千円で売ろうというのだ。
人間として許される行為ではない。
いうまでもなく、わたしはきっぱり断ろうとした。
しかし、このS氏、実在する人物とは関係ないことになっているので判然としないのだが、目的を達成するためならなにをしでかすかわからないところがある。
そこで、根が小心なわたしはついついネタまで考えてしまった。
とはいえ、コピー誌千円などという邪悪な計画に荷担するのはやはり嫌である。コピー誌に念を入れた、と思われるのはもっと嫌である。それぐらいならハードSF書いてコ○ノケ○イチに捧げてやる。
逃亡者であるがごとく、安穏とは縁遠い生活が始まった。
「さあ、とっとと書いて、一冊一冊、念を入れるのだ」といついわれるか。それを思うと夜も眠れなかった。眠れないのでついアルコールに頼り、酒に溺れる毎日。
もうこんな生活はいやだ。
わたしは決意した。千円コピー誌に書かされるはずだった小説をいまここで発表してしまう。
というわけで、以下の小説は『星界の紋章』『星界の戦旗』を読んでいないかたには無意味だと思う。責任の一端はわたしにあるが、残りの長い部分は架空の人物ということになっているS氏にあることをご理解いただき、なにとぞご寛恕を賜りたい。
谷甲州黙認FCの年会誌を買ったつもりなのに、なんのことやらわけのわからない短編が載っているだけでもじゅうぶんお気の毒だと推察するので、せめて念をこめるのはやめておく。
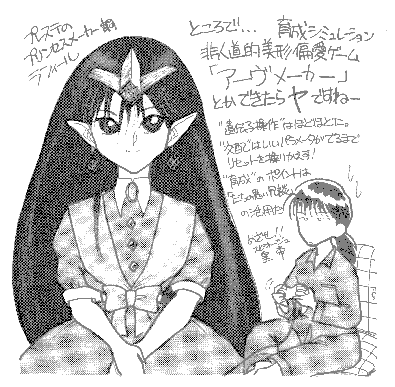
『星界の紋章・超外伝
饗宴』森岡[星雲賞にノミネートされて、ゲストになれなかった男]浩之
〈混沌の都〉、〈竜の頸の付け根〉、〈八門の都〉、〈帝国の揺籃〉、〈陥ちざるもの〉、〈愛の都〉、〈故郷〉――帝都ラクファカール。
この都市では、招待状の要らぬものだけを考えても、饗宴の開かれぬ日はない。豊かな貴族は帝都に留まっているかぎり、すくなくとも年に一度は饗宴を催すのを義務と心得ていたし、さほど豊かでない者もなにかにつけて費用を出しあい、人々の記憶に残る日を設けようと競っていた。
毎年開かれるもろもろの饗宴のうちで、人々が心待ちにするものがいくつかある。帝宮を開放して行なわれる園遊祭、富裕で名高きソスィエ一族が総力を尽くすケヒュール記念饗宴、奇抜な余興が客たちを魅了してやまないボーフ伯爵家の饗宴……。
だが、もっとも多く人々を集めるのは、まったく豪華でもなく――なにしろ料理も酒も出ないのだ――、まったく趣向もない――余興ひとつあるではない――宴だった。ただ会場だけは抜群に広い。にもかかわらず、歩くにも苦労するほどの人数が会場を埋め尽くすのだ。
それはソビークと呼ばれ、年に二回開かれるのを常とした。銀河の大部分の民にはうかがいしれぬ理由で、星たちの眷族はソビークをかけがえのないものと見なしている。
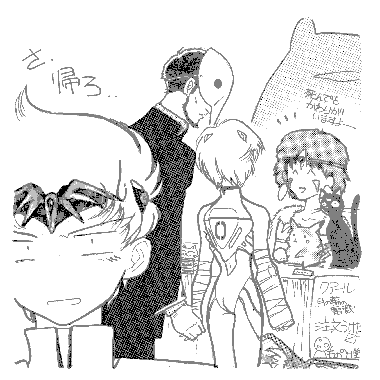 「これがソビークか……」噂に名高き饗宴にはじめて参加したジントは、物珍しさに辺りを見まわす。
「これがソビークか……」噂に名高き饗宴にはじめて参加したジントは、物珍しさに辺りを見まわす。
空間に浮かぶ住居や船にわかれて住むのを常とするアーヴがこれほど多く集まっているのを、ジントは見たことがなかった。さらに目を引くのが、彼らのまとう衣装だった。
アーヴの服装は単純だ。だいたいにおいてつなぎを着ている。貴族なら長衣、士族なら短衣をつなぎのうえに着ることもある。だが、この場においては、つなぎのかわりに異様な風体をしている者もちらほら見えた。異様な、とはむろんアーヴの基準をもとにしての話ではある。しかし、いったいどこの社会でなら異様でないのか、見当もつかない服装も見えた。
ジントのすぐ右手には人垣ができていた。のぞいてみると、とりわけて奇妙な衣服をまとった少年が中心で気取って立っている。人々は彼を撮影するためにわざわざ輪をつくっているようだ。
ジントはまたひとつアーヴの秘密を垣間見た気分になる。
ジントがこの饗宴に来たのにはとくに深い理由はない。彼は仮にもいちおうアーヴ貴族なのだから、一生に一度ぐらいはこの帝国に名高き宴に参加してみるべきだ、と思いたったのだ。そして、参加するのは一生に一度でじゅうぶんだ、と結論を出しかけていた。
なにしろ人混みがすごい。船を移動の手段というより生活の場と見なすアーヴは、わりあいと混雑に慣れているようなのだが、ジントはまだ非アーヴ的な部分をかなり引きずっていた。
押し出されるようにして、ひとつの机の前に来た。机のうえには本が積みあげられていた。もはや博物館でないと見ることができないような紙の本だ。どういうことなのかジントにははっきり理解できないが、「紙の本を出展するのが伝統」なのだそうだ。『一冊二〇〇シェススカール』と値札がついている。
手にとって、ぱらぱらとめくってみる。
大きな単色の絵がある。あまり写実的な作風とはいいがたく自信はないが、どうやら男性らしい。その周囲は細かい手書きのアーヴ文字で埋め尽くされていた。一読してみる――よくわからない。
ジントは本をそっともとの場所に戻す。そのとき、机のむこうに坐る少女と目があった。少女は哀しそうな眼をしていた。
「いや、その、ほら……」ジントは笑ってごまかし、その場を足早に立ち去った。
この饗宴には三種類の人間がいる。売り手と買い手、そしてそのどちらでもない者。ジントはどうやら最後の組に入っているようだ。
人の流れのままに歩く。ときどき視線を感じる。「買ってくれないかな」という熱のこもった視線だ。アーヴは戦闘種族である以前に商業種族のはずだが、声高にものを売りつけないのが、ソビークでの正しい振る舞いらしい。
じつにありがたかった。ただでさえ人いきれに疲れているので、断る気力もない。
ソビークで売られているのは、ほとんどが紙の本だが、それだけではない。少数ながら記憶片を売っている机もあった。だが、その内容は、紙の本では記しきれないものに限られているようだ。
耳の長い猫や額に三日月の入った猫を売っている机もある。もちろん、生きている猫だ。一瞥すると、『同人制作……』とか書いてある。
外道――ジントは思った。
左右に視線をさまよわす。人混みのあいだから、『包帯は永遠に』だの『たぎる血が熱いぜ!』だのと理解不能な語句が目に飛びこんでくる。
見るべきほどのものは見た――ジントは結論をくだした。きっとある種の人々にはたまらなく楽しい饗宴なのだろうが、彼には楽しめないたぐいのものなのだ。
ジントは帰ることにしたが、それがまた容易ではない。出入り口からはるかに離れてしまっている。
人をかきわけつつ、ジントは困難な作業に挑んだ。
ようやく半分ほどの旅程を消化したころ、ジントは驚いた。思いもかけず知り合いと出会ったからだ。
「ラフィール!」ジントは声をかけた。
人類史上に比類なく強大な帝国の帝室の一員として生まれながらにパリューニュ子爵の称号を帯びる少女はぎょっとした顔で振りむき、なにかを背中に隠した。「そなた……、なぜここに?」
「なぜといわれても、べつにたいした理由じゃ……」
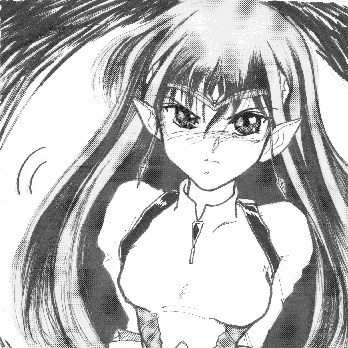 ジントが説明しようとしているあいだに、ラフィールは一時の動揺から立ちなおる。
ジントが説明しようとしているあいだに、ラフィールは一時の動揺から立ちなおる。
王女の眉が危険な角度に逆立つ。「見損なったぞ、ジント」
「な、なにが……?」ジントは目をぱちくりさせた。
「そなたがこんなところに来るとは思わなかった!」ラフィールは肩をそびやかす。
「ええと……。ひょっとして怒っているの?」
「べつに怒ってるんじゃない。ただ、そなたがこんな人間とは思わなかっただけだ」
「そんな人間って?」ジントは呆気にとられたが、それよりラフィールが背中にまわしている腕のことが気にかかった。「それって、今日の買い物? よかったら見せてくれよ」
「よくない!」ラフィールはじりっじりっと後ずさりはじめる。
「まあ、見せたくないなら、それでいいけど」ジントは紳士的な態度をとり、「ところで、久しぶりで会ったんだ。お茶でもどう?」
「そなたは非常識だな」と呆れたように、「お茶などどこででも飲めるじゃないか」
「そりゃまあ、おっしゃるとおりだけど」
「ソビークにまで来てお茶を飲むなど信じられぬ」
「そこまでいうことないじゃないか」ジントは一歩、ラフィールに近づいた。すると、ラフィールも一歩下がる。
嫌われたかな?――ジントは途方に暮れた。
「近寄るでない!」ジントの懸念を裏づけるように、ラフィールはきっぱりいった。
「そうか……」ジントはうなだれた。まったくこの饗宴では理解できないことばかり起こる。なにも悪いことをしたおぼえがないのに、いつのまにか王女には嫌われている。ひょっとして、自らの行動のわけのわからなさを競うためにこの人々は集っているのではなかろうか。
ジントはきびすをかえした。
「どこへ行くんだ?」とたんに呼び止められる。
もしかしたら嫌われていないのかもしれない――一縷の望みを胸にいだいて、ジントはふりかえる。「帰るんだよ。もう用はないから」
「怒ったのか?」心配げにラフィールの眉が曇る。「でも、そなたもいけないんだぞ。人の買ったものを見たがるなんて、趣味が悪い」
「いや、べつに、どうしても見たいってわけじゃ……」正直なところ、ただ話のきっかけにでもなればよかったのであって、ラフィールがなにを買ったかということ自体にはさほど関心がない。どうせ、ジントには理解できないものにちがいないのだから。
「見たくないのか?」漆黒の瞳がじっとこちらを見る。理不尽なことに、ラフィールはすこし傷ついているようだ。
どうこたえれば満足なんだろう――ジントは悩んだ。いっぽうで安心してもいた。どうやら嫌われたというのは早とちりだったらしい。彼女はとにかくこの饗宴の成果を見られたくないだけなのだ。もっとも、なぜ見られたくないのかは見当もつかなかったが。
「ええと、その、見せてくれたらありがたいと思うけれども、無理には見たくない」ジントはなんとか無難らしい答えをひねりだした。
「そうか、そなたがそういうんならしかたがないな」ラフィールは背中に隠していた紙袋を差し出し、「特別に見せてやる。感謝するがよい」
「ああ、ええと、ありがと」ジントは受けとって、さっそく中をのぞこうとした。
「ダメだ!」とたんに王女が制止する。「見るのはあとにするがよい。ソビークが果てるまで荷物持ちをするなら、見せてやる」
「荷物持ちでもなんでも」ジントはうやうやしくいった。ソビークに来たかいがあったように思えてきた。
「じゃあ、しっかり持ってるがよいぞ」
机に群がる人混みに突撃するラフィールの背中を見送って、ジントは微笑む。〈人類統合体〉の追っ手から逃れる日々に見たものとはちがう、王女の一面を見て、得をした気分だった。
しかし、間近に迫った未来を知ることができたなら、彼は顔をほころばす余裕などなかっただろう。
ラフィールの買い集めた品々――もっぱら紙の本だったが――はやはりジントには価値を判断しかねるものだった。それはじゅうぶんに予測できたことだったが、この理解不能の本たちに興味があり、それを手に入れた王女をうらやましがるフリをしなければならないという難行苦行がジントを待っているのだ。
【おわり】
(筆者註:この作品はフィクションであり、実在の人物・団体と関係ないことはいうまでもないことですが、とある小説の登場人物とも無関係だと力説させていただきます)