

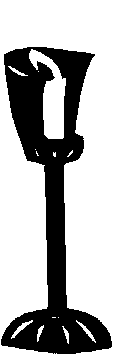 |
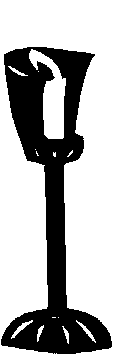 |
|
 |
数日ほど夕立のない暑い夏が続いていた。東京も市中はやたら埃が目立つようになり、銀座の煉瓦なんぞ妙に熱を持って、町全体がうだっているかのようであった。
「暑気払いにはね、やはり怪談でしょう」
ぱたぱたと団扇で顔をあおぐのは、物書きの仮名垣魯文である。
「馬鹿言ってんじゃねえよ、幽霊咄で涼しくなるんならよ、米次郎の家なんざ年中寒いことにならあ。だが、見てみろ、銀座は暑くてどうしょもねえぞ」
ひいひいと、顎を出しながら返事をするのは河鍋暁斎。絵描きである。
明治十二年、この年の夏は妙に暑かった。二人の男は、うだる暑さの銀座をそぞろ歩いている、と言えば聞こえはいいが、実際は本の版元に挨拶の帰りであった。
暁斎が、米次郎と言ったのは、彼の兄弟弟子である月岡芳年のことである。彼の家は、この銀座のすぐ裏に在る。その芳年は、幽霊が出ると騒いで、屋移りを繰り返したという話である。今の家にも出るのかどうかは知らないが、以前の家もすぐ近所であった。「まあまあ、そうかりかりしなさんな。もう円朝さんには話をしてある。やはりこういうのは本職の人間にやらすに限るからねえ」
暁斎が驚いて魯文の方を見た。
「なんでい、おめえにしちゃあ妙に手際がいいじゃあねえか。はは、裏でなんか企んでやがんな」
魯文は慌てて団扇と手を同時にばたばた振った。
「ないない、何もない。俺は純粋に怪談が聞きてえんだよ」
嘘である。魯文、嘘をつくと目が宙をさまよう。暁斎の絵描きの観察眼がこれを見逃す筈もない。暁斎、何も言わずに魯文の後頭部を手にしていた扇子で叩く。
「三文文士、もっと上手に嘘を付け」
「いてえなあ、暁斎さん、あんた川越から帰ってから妙に人が荒いよ。向こうでなんぞあったのかい?」
「何もねえよ、酒もたらふく飲めたしな」
魯文は、ははあと察した。どうせ旅で路銀を使いすぎ、家に帰ってからあまり酒にありつけていないと見える。そこで魯文、一計を案じた。
「酒といやあ、百物語には精進落としの酒がつきものだよな。円朝さんが来てくれるとなれば、あちこちの席亭から樽が届くんじゃねえかな」
計略は的を得た。暁斎の耳がぴくりと動いた。あと一押しである。
「それに、どうせやるなら場所も凝らねえとなあ。おめえさん家の近くの霊雲寺なんて広くていいんじゃねえかな」
暁斎の足が止まった。
「この悪党め。どうやっても俺が断れないようにしてやがんな!」
どうやら暁斎は観念したらしい。この湯島の霊雲寺には多数の仏画があり、暁斎は日頃から住職に見せてくれとせがんでいるのだが、なかなか首を縦に振ってもらえない。仏門に入るか、檀家にならなきゃ駄目と言う。だが、今の時期ならそれらの仏画は、庫裏の中に虫干しされている筈である。
「じゃあ二、三日したら日程を知らせるよ」
 魯文はそう言ってにやりと笑った、明らかに何かを企んでいる顔である。
魯文はそう言ってにやりと笑った、明らかに何かを企んでいる顔である。
怪談会が催されたのは、それから五日後であった。夕方になり、暁斎は自宅から下駄を引っ掻けて霊雲寺に向けて歩きだした。
逢魔が時、たそがれの闇の中には人間でないものの気配が潜んでいた。
「絵描きの大将、おでかけかい」
闇の中から声がかかる。ただしこの声、暁斎以外の人間には聞こえないかもしれない。
「ん? なんでい、むじなの小僧か、じいさんは元気か?」
闇の中に、丁稚姿の子供の姿が在る。ただし、この子供、人間では無い。なにしろ小僧、顔がない。
「じいさんは、暑いんで伸びてるよ。もうかれこれ十畳敷きくらいには伸びてる」
暁斎は、一瞬きょとんとしたが、すぐに前に突き出た歯を揺らして笑い出した。
こののっぺらぼうは、暁斎の友人の孫である。その友人というのが、東京市中の妖怪を束ねているむじなの大将なのである。これが伸びている、文字どおり伸びているということは、あの巨大な袋を伸ばしているという訳だ。
妖怪が友人と言うのも妙なものだが、この異能の絵描きにとって、人間だ妖怪だという垣根はあまり関係ないようなのである。
「それより暁斎さんは、何処に行くんだい?」
「ああ、これから霊雲寺で怪談会だよ。化け物の話を聞きに行くのさ」
のっぺらぼうは不思議そうに首を傾げた。
「暁斎さんなら、ひと声かければ庭一杯の化け物が集まるのに。なんでわざわざ化け物の話なんか聞きに行くの?」
暁斎思わず苦笑した。まあ東京広しと言えども、本物の化け物に「人望」の在る人物は彼くらいのものだろう。
「人間には人間の付き合いが在るのさ」
暁斎、そう語ったところで、ある妙計を思い付いた。
「おい小僧、今この近所に暇そうな化け物は他に居るか?」
のっぺらぼうは、腕組みをした。
「ううん、どうかなあ。 不忍池の河童さんたちはゆだっちゃって動くの嫌そうだったし、家付きの網きりとか垢舐めなんて連中は書入れ時だからなあ。暇なのは、おいらみたいな半人前だけじゃないかな」
「なんでい最近河太郎来ねえと思ったら暑気あたりけえ。まあいい、ちょいと悪さするだけだ、おめえらでも十分だろう。ちょいと耳貸せ」
暁斎、のっぺらぼうの耳に口を寄せ、なにやらごにょごにょ説明した。
「あはは、面白そう。いいよ、仲間を集めてみるよ」
のっぺらぼうはそう言うと、その場でどろんと消えてしまった。
「ふふふ、さて乗り込むとするかね」
暁斎は、ぱんぱんと浴衣の袖を内から引っ張ると、にこやかな顔で歩き出した。
暁斎の家から寺まで、ほんの十分の道のりだ。彼はたちまち寺に着く。
「およよ」
山門の前に、墨痕鮮やかな看板がしつらえてあった。
「三遊亭円朝大怪談会、なんとまあ…」
魯文の筆跡である。もしかしてと思い、暁斎は看板の下の方を見る。
「あの野郎、大した商売人だ」
看板の下には、小さな文字で木戸銭二十銭と書かれていた。魯文は、この会を最初から商売として考えていたのである。暁斎は、その箔付けに呼ばれたという訳らしい。
「ああ、暁斎さん、やっと来たね」
寺の中から魯文がニコニコした顔で出てきた。
「盛会のようじゃねえか、え、席亭さんよ」
魯文に皮肉が通じる筈もない。
「中には酒が用意してある。円朝さんも弟子と一緒に来ているから、さっさと上がってやってておくれ」
魯文はそう言うと、いかにも忙しいと言った風に去って行った。暁斎は仕方無いといった感じに肩をすくめ、寺の中に入って行った。
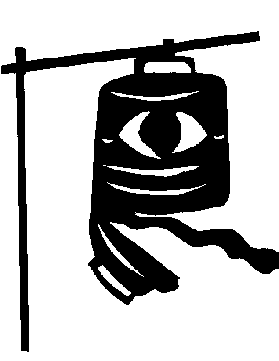 寺の中は盛会であった。よく見ると、版元や料亭の席主など見知った顔もちらほら見える。席の上座に、暁斎の友人である噺家の三遊亭円朝が座っていた。
寺の中は盛会であった。よく見ると、版元や料亭の席主など見知った顔もちらほら見える。席の上座に、暁斎の友人である噺家の三遊亭円朝が座っていた。
「よう円朝さんよ、あんたもまんまと乗せられたね」
隣に腰を下ろしながら、暁斎が円朝に言った。彼も苦笑しながら答えた。
「やられたね、仲間内の会だとか言われて、ロハで受けてしまったよ。でもいい勉強になりそうだから、弟子に噺をやらせてみるよ」
「まあ、魯文さんの口車に乗った我々が馬鹿だったってこったあな」
そこに魯文がやってきた。
「住職が見えたので、そろそろ始めましょう」
暁斎が改めて室内を見回すと、すでに青い紙を張り付けた行灯が百個並んでいた。
青い薄紙を通した明りは、部屋を不気味に染める効果がある。暑さを忘れる為の工夫という訳だ。この居並んだ行灯は、話が一つ終わる度に一個づつ消されていく。そして
最後の一個が消えた時、怪異が起こるという。この為、通常は九十九話で終えるものである。
「では、円朝さん、おねがいします」
魯文に促され、円朝の噺が始まった。
後世、怪談話の名人として語り継がれる事になる円朝。さすがにその語り口は、名人と称されるだけのことはある。観衆はたちまち、その噺に引き込まれて行った。
噺は、どれも短く終わる。それでも、一話ごとに客たちは背筋に恐怖を感じている様であった。
だが、暁斎だけはひたすら酒を飲み、時々噺に相槌を打つだけである。五話程語って、円朝は弟子に噺を引き継いだ。あらかじめ仕込んであるのか、弟子たちもいかにも恐い怪談を次々に繰り出して行く。
やがて行灯の数は半数以下まで減っていた。
「さて、ちょいと便所に行ってくらあ」
かなりいい気分になった暁斎は、ふらりと立上り縁側に出た。便所の手前あたりで、暁斎は暗闇に向かって何かぼそぼそ話し始めた。
「…てな手順だ。いいな」
ポーンと、まるで鼓を打ったような音が響いた。
暁斎が部屋に戻る。噺は延々と続き、やがて行灯の残りはもう数える程になる。時刻も既に深夜である。
円朝が再度噺を引き継いだ。そして、三つほど噺を進めると、ついに行灯は残り二個に減っていた。
「さて、これよりお話する噺にて、怪談も九十九話に達します。本日、結びの噺として、私自身が体験しました怪異をお話しいたしましょう。
私こと、怪談噺の名手などとおだてられますが、不思議とこういう噺をしておりますと、身近に怪異が集まるようでございます。別けても、絵に纏わります怪異、これは実によく体験致します。
別段、蒐集する気もございませんでしたが、幽霊を描き留めました書が、私の手元に多く集まるのでございます。これは、絵が仲間を求めているのではないかと思えるのですが、皆様はいかがお思いでしょう。
と申しますのも、こういった暑い夏の日など、軸を虫干しいたす訳ですが、こう何幅も壁に並べておきますと、深夜あたり、そうちょうど今頃の時刻になりますと、これらがざわざわと騒いでおるような感覚があるのです。
いえいえ、気のせいではないのです。或る夏の夜、寝つけぬまま、深夜に厠に立ちましたところ、この虫干し致して居ります部屋より、確かに人の声が聞こえてまいったのでございます。
驚きまして、この部屋の襖を開けてみますと、なんと一幅の絵の中より一本の青白い腕が伸び、私を手招きしているのです。
さすがにこれには大いに驚き、その場に座り込みうち震えるうち、朝の光が雨戸より射してまいりました。やれ助かったと顔をあげ、雨戸に手を掛けました。ところが、どうしたことか、開いてみれば外はまだ深夜の闇。さらに驚く私の背中に、掛け軸のある部屋よりけたたましき笑い声なぞ響き、お恥ずかしいかな、円朝は人事不肖になり翌朝庭先で家人に発見されたという次第。
「いやはや実にまか不思議な怪異でありました」
円朝が頭を下げた。それを認めて魯文が、九十九個目の行灯の灯を消した。そして、納会のために口を開こうとした矢先であった。
「そう言えばよう、さっき便所に行ったときなんだけどな」
いきなり暁斎が大声で話し始めた。それがあまりに唐突だったので、魯文は話を切出す機会を失ってしまった。
「本堂の奥の御本尊さんを拝んだんだよ。そしたら、ここの仏像が世にも珍しいもんだって気付いたんだよな。住職さん、すまねえが、御本尊のいわれってえの説明してくれねえかなあ」
暁斎に言われ、住職はしきりに首を傾げた。
「はて、当寺の御本尊様はごくごく普通の大日像で、別段おかしな所はございませんと思うのですが」
「いやいや、そんなこたあねえだろう。杯持って、酒を煽る仏像なんてえのは、生まれてこのかた、他所で見たこたあねえ」
暁斎がそう言ってにやりと笑った。住職は、むっとして答えた。
「それは何かの見間違いでしょう。そのようなふざけた仏像があってたまりますか。戯れもたいがいにしてください。」
しかし暁斎は顔色を変えない。
「じゃあ、そこで酒を飲んでいるのは、なんなんだい?」
暁斎は、一座の一番下の席を指さした。すると、そこに金色に輝く本尊が座り、確かに酒の杯をあおっていた。
「な、なんと!」
一座が総立ちになった瞬間だった。
「さあ、これで百話だぜ!」
酔っ払いとは思えぬ素早さで、暁斎が最後の行灯を消してしまった。座敷はたちまち真っ暗闇になる。すると、妙な獣の叫びやら、青白いもやもやしたものなどが室内を飛びかい始めた。
「で、でたあ〜!」
一際大きいのは魯文の悲鳴。たちまち恐怖に駆られた客たちが、右に左に大騒ぎ、室内は騒然となってしまった。
「あははは、痛快、痛快!」
この騒ぎをよそに、暁斎はこっそり座敷を抜け出して、家路についていた。その後ろに小さな影がいくつか付き従っている。
「ご苦労さん。ご苦労さん」
暁斎は、その影のひとつひとつに労をねぎらう。どうやら、あの騒ぎの主は、この小さな妖怪たちであったらしい。つまり、すべては暁斎の仕組んだことだった訳である。
そして、彼が自分の家の前まで来たときだった。
「し、しまった!」
暁斎はあることに気付き愕然とした。小さな影たちが、
びっくりして暁斎から少し遠ざかった程、それは唐突な叫びだった。
「び、びっくりしたなあ、もう。絵描きの大将、いったいどうしたの?」
むじなの小僧がおずおずと暁斎に聞いた。
「ええい、客を騙すのに夢中で、仏画を見てくるのを忘れちまった!」
正確には、酒を飲むのに夢中であろうが、突っ込んでみても仕方ない。
この事件から二か月後、暁斎は突然仏門に入った。と言っても、これは方便。実は、霊雲寺の仏画を見るための手段であった。それがなにより証拠には、暁斎修行をまったくせずに日々般若湯を飲みふけったそうな。
ちなみに、この時の怪談会、怪異が原因で魯文は客に木戸銭を返却せざるを得なかったそうだ。この男、つくづく悪い友人を持ったものである。
おしまい