幽霊
中谷[従軍ハムスター]真理子
オリクチ先生は私が担当する外来患者だった。
オリクチ先生とは本名ではなくあだ名だ。彼が折口信夫(二〇世紀前半の日本で活躍した民俗学者だ)に傾倒していることに由来している。
診察室で「民俗学」を講義していく(診察をするべき私が講義を聞かされるのだ)彼は、私の勤める病院ではちょっとした有名人だった。担当になったばかりの頃は診察をさせるよう抗議したものだが、いつの間にかそれもしなくなってしまった。態度や口調から彼の病状を推測して処方しているが、こんなやり方でもとくに病状が悪くなるわけではなかったので、一抹の疑問と後ろめたさを感じつつも、いつの間にかそれが習慣となっている。
それにしても、奇妙な研究テーマとしか言いようがない。はるかかなたの地球のごく一部の地域の、しかも前世紀にあらかた失われてしまった民族独自の芸能や民話や祭りを二二世紀のガニメデで研究して意味があるとは思えない。彼が日系だということを考慮に入れたとしても。せめて中国かインドのそれならば研究の余地はありそうだが(太陽系中で彼らの祭礼は盛大に行われている)、オリクチ先生という人は頑固に折口信夫にこだわり、現実社会に背を向け折口の論文や研究書(高価な紙の本も所有していた)を読んで暮らしている。だから収入などあろうはずがなく、いつも顔色悪くやせていて、いつも同じコートで診察室にあらわれる。他人に迷惑はかけていないとは言え、別の意味で困った人だった。しかし、非実用的な学問の世界に没頭して社会との接触を最低限にすることで彼の精神はかろうじてバランスを保っていたのかもしれない。
そして告白するのには気恥ずかしさを感じるのだが、彼の語る海の向こうの(私は本物の海を見たことはないのだが)「とこよ」という異郷の話やそこからこの世を訪れる「まれびと」とよばれる人の姿をかりた神の話は心ひかれるものであり、いつの頃からか私はオリクチ先生と会うのを楽しみにするようになっていた。
しかし、彼はある時をさかいにふっつりと病院に来なくなった。病院を変えたのかと思い同業者にそれとなく尋ねてみたが、彼の消息を知る者はいなかった。私はなぜか破門されたのだと感じた。
数ヶ月後、見る影もなくやせ衰えた彼と再開した。栄養不良と脱水で動けなくなっているのを大家が見つけ、病院にかつぎ込んだのだ。検査の結果、胃癌と診断がついたが、肝臓だけでなく腹膜全体に転移していてもう手遅れであった。病名を告げると、彼はこちらが拍子抜けするくらいあっさりと安楽死を選択した。六六歳だった。
彼のデータを呼び出してみる。「二一〇〇年、三三歳で発病」とある。私が生まれる前から精神を病んでいたのだ。発病する前は軍工廠の造船技術者として働いていたらしい。時々はその知識を生かしてトランパーたちにアドバイスをしていたらしいが、最近はほとんど収入にならなかったのではないか。ここガニメデに限らず、木星系ではトランパー自体見なくなった。
カルテには彼の前半生の記録が続く。
父親は地球生まれ、母親は火星生まれ。結婚して地球に移住、第一子として彼が生まれる。数年で両親は離婚、彼は父親に引き取られた。母親はそれから間もなくガニメデで事故で亡くなる。父親は彼の成人後に亡くなり、その後彼は地球に戻っていない。
発病時の記録を見る。と言っても、病歴が長くあちこちの病院を転々としているので、病初期のことはどうしても曖昧になる(戦争をはさんでいるからなおさらだ)。動乱勃発から半年あまり過ぎた頃、彼は勤務中に突然錯乱状態となり、同僚にとり押さえられ病院にかつぎ込まれた。簡潔にすぎる記述だ。ジュノーの病院で治療を受け、終戦後にガニメデに戻ってきたらしい。
だいたい、ジュノーは動乱中は中立を守ったのではなかったか? そこにガニメデの造船技官がいたというのも不思議だ。つじつまが合わない。
次に掲げる文章は、上記の疑問をぶつけた私にオリクチ先生が語って聞かせてくれたことである。最後の入院の時のことだ。
「とこよ」といい、他界ともいう、ここではないどこか。私たちの魂のふるさと。いまだ目にしてはいないのに、懐かしい場所。
ヒトが、この世の向こうに別の世界を夢想するのはなぜか。折口信夫は簡潔にこう述べている。「人が死ぬるからである」。
あの戦争のあとは、太陽系はどこもかしこも死者でいっぱいだ。かつてヒトが至る前は真の真空であったところに、今日では死臭が満ちている。
私は、死んでいった者たちを思い、彼らが行ったのかもしれない、ここではないどこかのことを考える。古代人が海の向こうに「とこよ」を夢想したように、そして折口が大王が崎で直感したように、私は空の向こうにそれが「ある」と夢想した。いや、若い頃にはっきりそう感じてガニメデまで来たわけではない。なにもかも終わった今、ふりかえると、そうだったのかもしれないと思うだけだ。
子供の頃は人並みに外宇宙探査のクルーを夢見ていたが、ずいぶん早くにあきらめてしまった。自分の頭の出来に夢は持たなかったから。ませたかわいげのない子供であったと思う。
私は八〇年代最後の年に工学系の大学を卒業し、造船技術者の道を歩むことになった。
航空宇宙軍には入れなかった。不採用の理由は聞かされなかったが、片親が外惑星人であることが関係したのだと思う。ちょうど航空宇宙軍の外宇宙探査計画が凍結されていた時期だったので、その時はそれほど残念だとは思わなかった。
それに、当時は外惑星の方が社会全体が活気に満ちていた。各自治政府は貿易自由化の時代にそなえ港湾施設の拡充や保有船舶の増加に力を注いでいた。そのためか求人票を見ると地球周辺より外惑星での方が待遇はずっとよかった。
いずれ惑星開発局よりも各自治政府の方が大きな権限を持つようになる、そんな見方もあった。今では夢のような話だが、若かった私はそれを信じた。
私はガニメデの造船会社に就職した。半分国営みたいな会社で、宮仕えの窮屈さと役人じみた頭の固い上司にはうんざりもしたが、全体に悪い職場ではなかった。
そう、その後だ。地球-月連合と外惑星諸国の緊張が本格的に高まりはじめたのは。造船業の好景気も、今思えば来るべき戦争を暗示していたのだ。
…いつの頃からだろう、私まで戦争は不可避だと当然のように思うようになったのは。勝てないまでも、やり方次第では地球-月連合に大幅な譲歩をさせることができると信じるようになったのは。
外惑星連合の敗北は、やるまえから分かりきっていたのに。
動乱に、私は外惑星連合側の人間として参加した。選択の余地はなかった。
開戦の前後は、ドルトン・リッジ併設の工廠で毎日忙しいが単調な生活をしていた。私は大学出だったから、開戦の後中尉になってしまった。変わったのは肩書きだけで、仕事の内容も給料もたいして変わらなかったが。
食糧危機の噂が流れはじめても、造船技術者は優遇されていて食事はちゃんと出た(味気ないレーションだったが)。給料もきちんと支払われていて、仕送りする必要も使う機会もなかったので貯まる一方だった(敗戦で無に等しいものになったが)。
無邪気だったと思う。
トロヤ群が降服し、続いてタイタンも降服した。戦争の行方はもう誰の目にも明らかだったが、私はそれと自分の将来とを真剣に結びつけて考えたことはなかった。
地球が故郷だという意識はなかった。もう係累はいなかったし、戻りたいと思ったこともなかった。ガニメデに所属しているという意識も、正直なところそれほどなかった。社会の矛盾とかいうものはここにもあって、軽い失望をおぼえていた私は、戦争が終わったらどこか別の都市に移りたいと思ったり、どこに行っても同じだと思い直したりしていた。私は今までも一人だったし、これからも一人だ。造船屋が失業することはない。腕さえ良ければ、どこででも食べていける。そう信じるようになっていた。
そんなある日、ついに私も当事者として戦争に係わることになった。
いつものように見送る側ではなく。クルーとして。船と共に。
サラマンダー。
あの船は特別だった。
あの船には幽霊がのっていたのだから。
最初からあの船は特別だった。
とにかく手間のかかる船だった。なにもかも規格外れで、あらゆるものが最低一度は故障した。ほとんどのパーツが試作品みたいなものだったし、そうでないものも戦前より質が落ちていた。
タイタン製のエンジンもひどかった。マニュアルと呼べるものすらなかった。あったのは開発者たちの記したメモの山だけ。エンジンも試作品同然だったから、彼らもちゃんとは分かっていなかったらしい。開発総責任者のなんとかいう偉い博士は、結局タイタンから一歩も出なかった。それでも、タイタンが包囲される前は彼に照会することもできたのだが…。今思うと、タイタンは最初から戦争に乗り気じゃなかった。要するにそういうことだ。外惑星連合なんて、はじめから穴のあいた泥船のようなものだった。
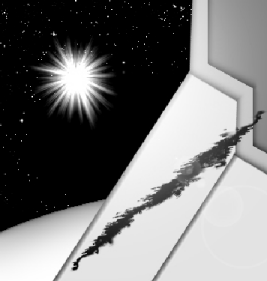 事故も多かった。
事故も多かった。
超過勤務が続き、誰もがいらだっていた。だから普段ならおこり得ないようなミスが起き、それが事故につながった。
資材キャリアの操作をあやまり、キャリアとサラマンダーに挟まれて横腹いっぱい(長軸方向だ)に引きずられた奴もいた。奴、ではなくて彼女だ。黒い髪。東洋系の。とくべつ親しかったわけではなかったが…嫌いではなかったから…。
次の直に、サラマンダーを挟んだむこうの仮設モジュールに行く途中で、船腹に昨日まではなかった下手くそな黒いラインを見つけた。しばらく見つめてから、それがマーキングではなくて彼女の血だと気づいた。今も明け方にそれを夢に見る。
そう、サラマンダーだ。
そんな具合だったので、工事は進まなかった。上の方からは毎日のように催促だ。かと言って、未完成なものを飛ばすわけには行かない。戦争だ。遊覧飛行じゃないんだ。
だが、公試も訓練もそこそこに、出撃の日程が決まった。工廠と軍と、誰がどういう話し合いをしたのかは知らない。乗員を最小限にして、造船技術者が乗り込むことになった。私たちが。無茶苦茶だ。
だが、私は…誰かが行かなくてはならないのなら、自分が行きたいと思った。いや、行かねばならないと思った。
今思うと、私はすでにしっかりと捕らえられていたのだな。
…幽霊に。
幽霊に気づいたのは、いつだったろう。
公試と訓練とをかねた短い航宙の度に、手直しするべき箇所だの故障だのが後から後から出てくる。サラマンダーが帰港すると私たちはあわただしく艦に乗り込み、次の出航に間に合わせるために不眠不休で工事をした。
たまにベッドにもぐっても、すぐには寝つけなかった。直前の作業風景が次々と脳裏に浮かび、いつの間にか次の作業の段取りを考えたりしている。思考が論理的でなくなっているのに気がつき、それで自分が夢を見ているのだと気づき、つづいて目覚ましのアラームが鳴っているのに気づく。そんなことの繰り返しだった。
その頃から、背後から見つめる視線は意識していた。
視線を意識し始めると、景色の現実感が薄れ、魂だけの存在になったような頼りない心持ちになる。それにも関わらず、やるべきことが目の前に次から次へと浮かび、手足は素晴らしい早さと正確さでそれをなぞる。まるで、自分で考えたり手を動かしたりしない方がいい仕事ができるかのように。疲労はなかった。飽きることもなかった。ただ、視線を背中に感じつつ、私の手足は別の生き物のように猛然と動き続けて…その時私はどんな顔をしていたのだろう。ぼんやりとしていたろうか? それとも、至福の表情を浮かべていたろうか?
もちろん、はじめは困惑した。合成アンフェタミンのせいかと思った。あれは良くないな。全体を見渡すことができなくなる。延々とリベットをうち続けるなんて時には悪くないが。「考えて」仕事をしたいなら、やめるべきだな。
そう、幽霊だ。
はっきりとそれを見る前から、何かが違う、とは思っていた。何かが起きつつあった。それがいいことか悪いことかは分からなかったが、出撃の前に艦を少しでも完全に近づけるべきだ、とは強く感じていた。それは政府への義務ではなくて、造船屋のはしくれのプライドだ。…今思えば、それだけではなかったのだが。
その働きぶりが認められたのだと思う。私はサラマンダーに乗り組むことになった。
辞令を受け取ったときには、特に感慨はなかった。予測していたから。若くて、熟練していて、家族も恋人もいない私は、きっと選ばれるだろうと。心配だったのは、私が地球生まれで成人してからガニメデ国籍を取ったことだった。しかし、心配することはなかったようだ。父が死に、地球にはもう係累はいなかった。既に調査してあったに違いない。
それに。
…私は呼ばれていたのだ。
……幽霊に。
出航前のことは特に思い出すこともない。持って行くべき私物なんていくらもなかったし、未練もなかった。サラマンダー(と幽霊)とともに行くのだ。大事なのはそれだけだった。
出航から数百時間は単調な航海が続いた。
ちょっとエンジンその他の機嫌を見て、あとはベッドにもぐりこんで乗員の邪魔をしないよう、酸素を無駄に消費しないよう心がけるだけの日々だった。
 そんなある日、幽霊を見た。
そんなある日、幽霊を見た。
通路の先に、それはエンジンが生み出すGなぞ無縁な様子で立っていた。うつむいて。黒い髪。東洋系の。
怖くはなかった。ああ、やっぱり、と思った。視線の主に、やっと会えたのだ。
遠い昔、進水式の際には生け贄を捧げたと聞く。シャンパンなんかで代用する前の時代だ。太平洋の航海民族は、船に宿り航海の行く末を左右する精霊の存在を信じた。最先端技術でいっぱいの最新鋭艦といえども、船としてしっくりと「ある」ためには、員数外の1が必要なのだ。絶対に必要なのだ。これはこの先も決して変わらない原則だ。
ほのめかしの時期は終わり、すべての断片があるべき場所に収まって一つの風景が浮かび上がった。幽霊がここにいるのは必然であり、私がここにいるのも必然である。そう確信した。
それからはいつも幽霊を見た。眠るとき、忙しく立ち働いているとき、ぼんやりとしているとき。それは通路を遠ざかっていく後ろ姿だったり、視界の端をかすめる黒い髪だったり、扉が閉まる直前に一瞬向こうにのぞく横顔だったり。おそらく、前からそこにいたのだろう。見つけるつもりで見ないとだめなのだ。一面の点の中に立体像が見えるステレオグラムという遊びに似ているかもしれない。
もちろん、こんなことは誰にも言わなかった。「精神に変調を来したため」下船を命じられてはたまらない。私は、サラマンダー(と幽霊)とともに、最後までゆかなくてはならないのだ。
戦闘がはじまる。
殺気立つ乗員を遠目に見て、私たちは邪魔にならないようにベッドで手足を縮めていた。加速。長い加速。振動で、爆雷が放たれたことを知る。
振動に混じるかすかなきしみに私は船の不調を予感したが、意志の力では指一本動かせなかった。この瞬間にも、私に死をもたらすために爆雷の破片が虚空をこちらに向かっているのかもしれないのだ。目も見えず耳も聞こえず、毎秒毎秒を死の予感におののきながら過ごすのがこれほどの苦痛だったとは。
恐ろしい光景が次々と脳裏に浮かんだ。今まで耳にした様々な死の光景が、あたかもこの目で見た風景であるかのように。敵味方を問わず、指揮官にも兵にもそして飛び入りの造船屋にも死は等しく訪れる。ああ、脳裏に浮かぶ死体は、みな私の顔をしているではないか!
私は固く目を閉じた。そうすれば、恐ろしい光景を見ずにすむかのように。
幽霊が来た。胎児の姿勢でふるえる私のそばに…ベッドに赤い血がしたたる…顔を寄せ、何事かささやこうとする。固く目を閉じても、顔を背けても、逃れられない。
その言葉を聞いてはいけない。
なぜかそう直感した。それは不吉な予言なのだ。聞いてはいけない。
だが、無慈悲にも幽霊は告げた。
もはや永遠にとりかえしのつかないことが起きたと。
その声は、船を揺るがし、太陽系全体に響きわたるかのようだった。
あれは夢だったのか?
おそるおそる目を開けたが誰もいなかった。幽霊も。心臓は早鐘のように鳴り、体中を冷たい汗が流れた。いくら息を吸っても肺に血液に脊髄液に脳細胞に酸素が酸素が行き渡らない。手足が冷たくしびれ、意識が遠のく。それは私の咎なのか? 私の?
再び加速。エンジンの遠い響きのみ。返事はない。
その戦闘は我々の勝利だった。
だが私には遠い世界のできごとのようだった。すでに致命的ななにかが起きてしまっていたから、その後でいくら勝利を重ねても運命を覆すことはできない。もう遅いのだ。
私を縛る視線はつねに感じていたが、もう幽霊を目にすることはなかった。
エンジン出力は期待される値に達しず、私たちは対応に追われた。水の中にいるように酸素はつねに不十分で(空気浄化装置の修繕は完全だったのに)、手足は鉛のようだった。
だが私は職務にはげんだ。もはや動かしがたい破局が私のもとに至るそのときまで、せめてサラマンダー(と幽霊)とともにいるために。
サラマンダーは、タンカーとの邂逅に失敗した。
エンジンは不調。燃料も足りない。そして背後には航空宇宙軍。太陽系中の艦隊がサラマンダーを目指して集まってきていた。残された選択肢はいくらもなく、艦長はジュノー入港を決断した。ジュノーに抑留されている情報収集船から燃料を補給するのだ。
ジュノーまであと三〇時間を切った頃、武末中佐が私を呼んで言った。
「ジュノーで降りてもらいたい」
いやだ。
「…命令だ」
いやだ。私はこの船と(幽霊と)はなれたくない。
中佐は私を見つめたまま黙ってしまった。こういう場面で口数多くしゃべる人ではなかったし、私こそ幽霊のような顔をしていたのかもしれない。もっとも、その頃は誰もが疲労と緊張で幽霊のような顔をしていたのだが。
中佐との話はそれで終わり、私は一時、不幸は回避できたのだと信じた。
ジュノーに入港し、あわただしい時間が過ぎた。忙しいのは嫌いじゃない。色々考えずにすむ。それに、サラマンダー(と幽霊)と再び宇宙に出ることができると信じていた。すべてが失われ、もはやなにもかもが取り返しのつかない今でも、それだけは残されている。
作業が一段落したときに、武末中佐から艦長の決定を知らされた。
一瞬、意味が分からなかった。
今でも、具体的に中佐がどう言ったのか思い出せない。この前後の記憶は曖昧だ。私は…絶叫し中佐につかみかかって行ったのだと後から聞かされた。とにかく、尋常でない様子の私は同僚からよってたかって押さえつけられ、後からあたふたと駆けつけてきた軍医(彼のおびえた表情だけははっきり憶えている)に鎮静剤を打たれ、私は意識を失った。
私が再び意識を取り戻したとき、全ては終わっていた。
サラマンダーは私たちを残し飛び去った後だった。
数日後、入院中の私を武末中佐が見舞った。偽名を使っていた。中佐は間もなくジュノーを立つと告げ、そっけなく事実と、ふたことみことなぐさめめいたことを言ったような気がするがよくは憶えていない。
今思えば(いつもそうだ。大切なことにはいつも後から気がつく)私に会いに来るなんて、危険な行動だったのではないか。さらに後になって、彼は私の母を知っていたのではないかと思いいたったが、ついに尋ねる機会はなかった。
私は残りの入院期間、薬漬けの夢の中で、虚空を飛び続けるサラマンダーと艦長と、私の幽霊のことを考えていた。私には、サラマンダーのゆく先こそが「とこよ」といい、他界ともいう、ここではないどこか、私たちの魂のふるさとのように思えた。
私は艦長がうらやましかった。本当にうらやましかった。
その後は、自分の番が来るのを待っていただけのようだ。
いや、はっきりそう感じて生きてきたわけではない。なにもかも終わった今、ふりかえると、そうだったのかもしれないと思うだけだ。
話はこれでおしまいだよ。さよならの時間だ。
オリクチ先生の言うことが真実であるとすれば、彼は外惑星連合の唯一の巡洋艦、サラマンダーの関係者だったことになる。
サラマンダーは、最初で最後の出撃の後、ジュノーで乗員を退艦させたのち自沈した。退艦した乗員の中には造船技術者も含まれていたから、オリクチ先生の話はいちおうすじが通っている。
しかし、正直に言えば、私は全てが彼の妄想であると考えている(航空宇宙軍に採用されなかったのも、メンタルチェックで引っかかったからだと思う)。
もし彼が本当にサラマンダーの関係者だとしたら、中立国とはいえジュノーの民間病院でのんびり治療を受けていられるものだろうか? 航空宇宙軍に拘束されるか、外惑星連合軍の手で口封じをされるか、どちらにせよ無事に終戦を迎えられるとは思えない。
それでも、彼が数十年にわたって胸に秘めてきた物語(あるいは妄想)が誰にも知られることなく失われるのが哀れに思えて、がらにもなくつたない文章をつづってみた。戦後生まれの造船にも戦争にもまったくの素人が聞いてまとめたことであるから、オリクチ先生の語ったもとの話以上に間違いや矛盾する部分があるだろうことを、断っておかねばなるまい。
幽霊は、どんな顔をしていたのだろうか。
オリクチ先生の話では、事故死した同僚の幽霊(非科学的な!)のようでもある。しかし、彼は語らなかったが、幽霊は同時に母親の面影も持っていたのではないか。
つまり、彼にとっての「まれびと」は母親であり、彼は生涯「とこよ」すなわち母親の国へのあこがれを持ちつづけていたと解釈することもできる(つけ加えるならば、折口は「とこよ」の属性として数多くの矛盾するイメージを列挙しているが、その中に「慕わしい母の国」も挙げられている)。
さらに折口は「とこよ」=「常夜」として「死の国」のイメージをも持つと論じている。オリクチ先生にとり「とこよ」は死んだ母親の住む国であり、折口の説を引用するまでもなくはじめから「母の国」と「死の国」のイメージを併せ持っていたことになる。これは、彼の生への執着の少なさに多少なりとも関係していなかったか。…こじつけに過ぎるだろうか?
直接オリクチ先生にこれらの解釈を告げ、意見を求めるのは不粋な気がしてできなかった。だからこれは私の想像にすぎない。
私は思うのだが、外惑星にまで流れてくる人間は、二種類に分けられると思う。何らかの理由で地球にいられずに仕方なしに宇宙に出ていく者と、よりよく生きることのできる土地があると夢見て地球を後にする者と。
いや、人が一つの感情しか持たないと決めつけるのは愚かなことだ。誰にでも、二つの気持ちが様々な比率で混在していて…人によっては、どちらかを意識しないか、子供じみた感傷だと自ら否定しているのかもしれない。
私自身も、かつては後者の気分をいくばくか持ち合わせていたのを自覚する。自分がこれからおもむく未知の場所に、期待をこめ夢を見るのは誰でもすることだろう。そして、ほとんどの人間は現実に直面し、妥協する。どこに行ってもどのような職についても、それぞれの苦労や矛盾はあるに決まっている。それでもなお、くだらないしがらみと生活臭に満ちた現世との妥協をこばみ、虚空のさらに向こうにユートピアを夢想した(夢想せずにはいられなかった)ところにオリクチ先生の病理の一端があり、私が彼の話に魅せられた理由があるのだと思う。
オリクチ先生の遺体は再利用され、墓に納めるべきものはなにひとつ残らなかった。墓標もない。これは、彼の希望である。彼にとり、この世などはじめから仮の住まいでしかなかったのかもしれない。
 一般研究編に戻る
一般研究編に戻る
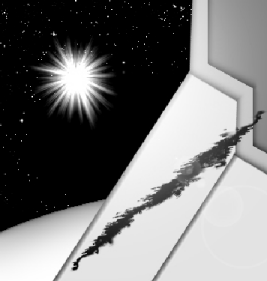 事故も多かった。
事故も多かった。 そんなある日、幽霊を見た。
そんなある日、幽霊を見た。