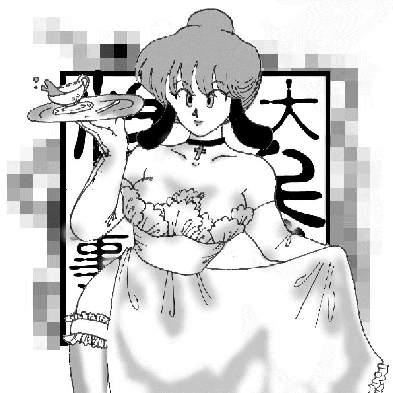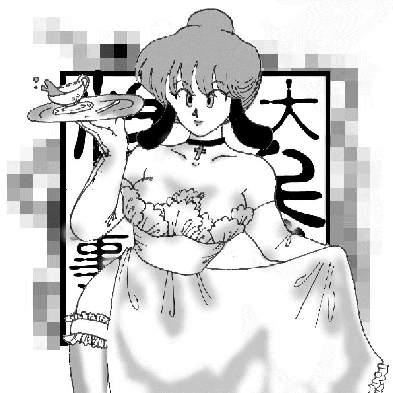
猫枕甲介はおぞましい悪臭のたちこめる部屋の片隅で、煙の昇る試験管をランプの光にかざしながら、「んふふふふふ」と含み笑いをしていた。ま、いつもの事だ。
私はソファからくそだるい身体を起こし、寝ぼけ眼を擦ると、頭痛がこみあげてきた。
――よく酸欠にならなかったなー。
「おはよう、ワトソンくん」と、甲介。その呼び方はやめてくれと言っているのだが、もう慣れてしまったらしく腹も立たない。慣れというものは恐ろしいもんだと私はつくづく思った。この同居人と顔を突き合わせるようになって数年経つが、もうたいていのことには驚かなくなっていた。
「さあ〜て、世界情勢は〜?っと」と私は枕元にあった今朝の新聞を広げる。そこには、
《巨人大勝! クワタ大笑い》
とあった。これで日本も安心である。わはははは。
「そうかね? あの女との結婚を諦めたのは、君にしてはいい判断だったよ。全く結婚は人生の墓場だからね」
甲介がやぶから棒にそう言った。さすが、人の事をワトソンと呼ぶだけの資格は持ち合わせているようだ。
「どうしてまた、そんな事がわかるんだい?」
彼はあやしい試験管を持ったままくるりと向き直った。その嬉しそうに輝いている眼の下のクマは、甲介がここ百時間ほど一睡もせずにマッドな実験に没頭していた事を示していた。
「僕はなんでも知っているんだよ、ワトソンくん。んふふふふ。まあ君が『なあんだ、そんな事か』とか後で言わんと誓うなら、種明かしをしないでもないがね」
「今月の家賃に誓って、そんな事は言わんよ」
「そんならいいがね」と甲介は手をひらひらと振って、「個々の推理は単純だし、それらを組み立てて一つの物語を構成するのだってさして困難なことじゃない。だがそんなものでも途中をすっとばして結論だけ聞かせてやれば、ずいぶんと劇的になるもんさ。簡単だよ。君は納豆のパックを一ダース買い込んでいたね」
「ああそうだが」
「そこの冷蔵庫に十一個も残っていた。賞味期限から逆算して、購入時期は約二週間前。これは君の寝顔がにやけ始めた時期とぴったり符合するんだ。納豆を賞味期限切れでだめにしてしまうぐらいだから、君は納豆は好きではない。ではあの納豆は何のためかと考えると、まあ君の恋人のためのものとしてまず間違いはなかろう。すると考えられる結論は以下の通りだ。恋人がナットー・イーターと知ってしまった君は、殊勝にも、納豆が食べられるようになろうと頑張ったんだ。その結果が君の初戦敗退に終わった事は、十一個も残っているんだから明白さ。だから君は、彼女と別れてきたと、わかるわけだ」
「どうしてもう別れた後だと言い切れるんだい?」
「君の左のほっぺたを見ればね、子供にだってわかるさ」
「なあんだ、そんな事か」
「今月の家賃も君が払っておいてくれたまえ」
「しまったあ」
「君が居てくれて本当に助かるよ。結婚なんか、しないでくれたまえよ」
「とほほほほ」
「ああ、それから、あの納豆はもう君には必要ないものだろうから、僕がありがたくいたたいておいたからね」
「あんたも納豆食い人種かっ?」
「ちゃうよ」と、甲介は手をひらひら振った。「かあいそうな君のためにと思ってね、見たまえ」
甲介は試験管の中の液体を一滴、納豆らしいものが入れられたビーカーに落とした。
ぼんっ!
そして、
なんともおぞましい事に、その納豆(らしき物体)は、うにうに動き始めた。
「ひー!」
「素晴らしい。これでこの納豆は生命を宿したのだ。しかも、強靭な繁殖能力と生命力を合わせ持っている。超高温・極低温などあらゆる環境にも適応し、おまけに核兵器にも耐える。酸への耐性があるから消化は不可能、人体に入り込んだこいつはその身体を内側から溶かし、納豆菌へと同化する。んふふふふふふ。こいつが世間に出回ったらどうなると思うかねワトソンくん。納豆を食おうなんて奴は一人も居なくなるに決まってるよ。そうすれば、君の恋人も納豆を絶って君のもとへ戻ってくるに違いない。んふふふふふふふふふ。まさに無敵のBC兵器! 世界征服の日は近いぞお。わあっはっはっはっはっはっは」
「あ、あたまが……」
その時ドアが開いて、この下宿の管理人さんがお茶を持ってきてくれた。
「御機嫌ですね、甲介さん」
「おお! ハドソンさん。ささ、ここに座って、乾杯しましょう、乾杯」
甲介は紳士らしく、管理人さんを椅子へと案内した。
私は口を押さえて吐き気をこらえる。「す、すまん甲介。き、気分が……」
「まあ」
駆け寄ろうとする管理人さんを甲介は手で制して、「僕にまかせて下さい、すぐ戻りますから。あ、そうそう、その机の上のビーカーね、絶対に触らないでくださいよ、絶対にね。さ、行くぞワトソンくん。まったくせっかくのハドソンさんのお茶だというのに、バチあたりな奴め」
甲介は私をかついで部屋を出た。
階段を降りていく途中で、乙女の悲鳴を聞いた。
そして西暦は終わった。