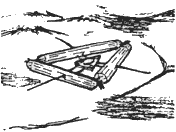 中国某地区上空で作戦行動中の「空中参謀」の図
中国某地区上空で作戦行動中の「空中参謀」の図 昭和初期、大陸に進出(または侵略)の駒を進める(または魔手をのばす)関東軍の仮想的はなんといってもソ連軍であった。
革命で疲弊しているとは言え、当時すでに二万両の戦車を保有する(ただし八割はオーバーホールが必要)ソ連陸軍は関東軍にとって何よりも脅威であった。
鉄鋼生産量だけをとってもソ連と日本では決定的な差があった。また陸路だけで補給が可能なソ連と異なり、関東軍は日本から補給を受けなければならないと言うハンディがある。
この補給線の問題を解決するために計画されたのが、戦争資材の効率的運用という思考であり、空中参謀なのである。
空中参謀とは一種の飛行船である。これは全長五十メートルの飛行船を一辺とする三角形から成り立っていた。この飛行船によって形成される三角形の内側にはアルミハニカム構造の完全与圧区画が用意された。
これを外から見たならば一辺五十メートル、高さ十メートルの三角形の箱に見えたであろう。この箱の各辺の真中には全長百五十メートルのアルミ製アンテナが水平に伸びていた。これが空中参謀の基本的な外観である。
さて、戦争資材の効率的運用とはなんであろうか?これは少ない戦争資材を有効に使うための指揮・管制・通信などの融合による有機的部隊運用、いまでいうC3Iに他ならない。
戦場における集中的な情報収集と、それに基づいた指揮・管制により歩兵・砲兵・戦車部隊・航空部隊の立体的かつ機動的運用により数的劣性をカバーしようとしたのがこの空中参謀なのだ。
空中参謀は通常は上空12000メートルにある。当時、大陸にはこの高度の飛行物体を撃墜できる高射砲も航空機もなく、また空中参謀そのものにも四連装二十ミリ機関砲が三角形の頂点にあたる部分に三機そなえられていたため、これが撃墜される恐れはなかった。 空中参謀の最大の特徴はその大アンテナである。今でいうところのシギントヤエリントをこの大アンテナにより行なうのである。空中参謀の受信能力からすれば敵の無線通信はほぼ完全に傍受することができた。
したがって敵の無線を傍受することで敵の動きが分かるだけでなく、敵の無線を妨害したり、欺瞞電波を飛ばすことすら可能だった。また上空からの戦場偵察の情報を地上部隊に流すことで効果的な部隊の運用が期待できた。
空中参謀の特色はまだ有る。空中参謀の三角形の真中にある直径にメートルの巨大反射鏡がそれだ。これは当時、神田在住のこの道五十年というガラス職人松岡源さん(仮名)が軍の依頼で一年がかりで磨きあげたもので、この時代の日本の光学技術の粋を集めたものだった。
これにより地上の様子が手に取るように分かるだけでなく、夜間でもその驚異的な集光能力により敵軍の動きを知ることができたと言う。
つまりこの空中参謀が有るかぎり、ソ連軍の関東軍への奇襲はありえないわけなのだ。 これらの望遠鏡による偵察結果は通常は特殊な落下傘で投下し、それを飛行機が回収していたが、緊急の場合は地上部隊にテレックスで送られた。
この時代の関東軍は中国人を野蛮な民族と思っていたため、この反射鏡のまわりには下から見ると巨大な目が上から覗いているような絵が描かれる予定だったと言われている。 この食う宇宙参謀は日本軍中央でも情報参謀を中心に高く評価され、すぐに建造にかかると思われた・・・が。
ある会議でのことだった。空中参謀の計画を聞いた東城英樹は計画担当者に、空中参謀から電磁石を降ろして戦車をひっくり返す、という自分のアイデアを採用するように強く主張した。
むろんこんな馬鹿な意見が採用されるわけがなく、この提案は無視された。しかし、これを根に持った東城英樹はひそかに運動しついに空中参謀計画を潰してしまった。
かくして世界初のC3I資材は幻に終わった。なお終戦末期に東城英樹は輸送船の被害があまりに多いため、輸送艦のまわりに漁網を巻いててき潜水艦の魚雷を防ぐという案を海軍に強く主張したが、むろんこんな馬鹿な意見が採用されるわけがなかった。しかし、当時、首相だった彼はこの案を実現するために影佐大佐なる人物に影佐機関なるものを作らせたが、結局この方法は実用化されなかった。
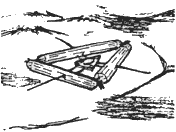 中国某地区上空で作戦行動中の「空中参謀」の図
中国某地区上空で作戦行動中の「空中参謀」の図
なおこれは陸軍の非公開資料に再録されたものである。現在まで「空中参謀」に関しては概念設計を含めた設計図はもとより、軍首脳への説明に使われたはずのイラストレーションなど、一切の絵画資料が残されていない。本図は「10月事件」の前後陸軍部内に流布された「粛軍」関連のいわゆる「怪文章」の中に収められていたものと言われるが、真偽は不明である。なお絵が非常に稚拙なのは細部の詳細を明らかにするのを嫌ったという説、描いたものが資料不足のため描けなかったという説の二つがあり、決着を見ていない。なお近年では単に描いた者の技量不足であるという新説が提出されている。