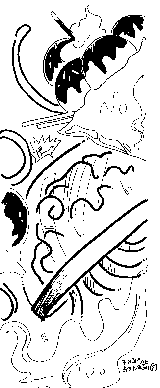
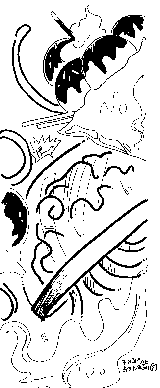
「ああ・・・納豆が懐かしいわあ」
ラザルスに一番最近組み込まれた、マリア・シソン博士が溜息のパルスと共に、思考を連結された神経コネクターに落とした。
「NATTOですか?」
ラザルスにおいては先住の、ジェイムス・ランドには、ようやく嘆き終えた女性(とはいっても既に体はないが)の、思考がプラスに向いたことは喜ぶべきことだった。なんと言っても、ラザルスは12人分の脳味噌の詰まった有機コンピューター(?)である。文字どおり[脳に直接響く女性の金切り声(しかも鳴き声)]に最初は同情したものの、四六時中聞かされた日には、イヤーウィスパーしたくてもする耳もない、遠くで酒をひっかけに行きたくてもする足もない、己の再認識をさせられているようで閉口したのだった。
「《なっとう》よ。納豆」
自分の落とした思考に反応したのが嬉しいのか、「」付でシソン博士は、ランドに返答した。
「確か、アジア圏の食物ですねえ」
元整備士だったハンス・ホルツァーがのんびりしたパルスで話のルーチンに入ってきた。
「ブルーチーズみたいな匂いがした気がするんだが・・・」
「ブルーチーズに、白ワイン・・・・ああ懐かしい」
ジアウル・ラクソンが。めそめそしたパルスでルーチンをくわえこんでくる。
女性の鳴き声の後に、男の愚痴・・・・などという最低な組み合わせをとっさに回避したかったランドは、あわててラクソンからルーチンを奪い取り、シソンにパスした。
「どんな食べ物なんですか?」
「大豆を醗酵させた食べ物でね、糸を引いてるのよ」
「私は、ロースクール時分に日系人の友人がいて、その子の家で食べたことがあったなあ」
ミシェル。ブルーハイムも、シソンに頷いた。
「ソイ・ソースをかけて混ぜるんですよ」
「なつかしいわあ・・・・・」
しんみりと、シソンが漏らす。
「味覚の感覚を再現してみましょうか?」
ピーター・ギゾムが、つんつんと各人へパルスを送った。
「そんなことできるのか?」
ラクソンが、沈んだ底から返事をした。
「味覚伝達が脳に達する時と同じ感覚を、再現できるパルスを送れれば良いのでしょう?」
ギゾムが乗り気で提案する。
「そうねえ、そうかしら?」
シソンが考え込む。
「取り合えず我々がよく食していたもので、試してみましょう。共通の間隔で微調整できますし」
ランドがまとめてルーチンを回した。
「ベーコン♪」
ホルツァーが嬉しそうに、[ベーコンを食べたときの感覚]をルーチンに乗せた。
「ううううううううううむ」
ランド達の脳裏に、べっとりとしてそれでいてカリカリに焼けた香ばしいベーコンがありありと浮かぶ・・・・。
「む・・・難しいなあ」
「後頭部にベーコンがこびりつく様だ」
「こんな味だっけ? こうじゃなかったっけ?」
ラクソンが、ひねったパルスを送る。
一同の脳の中に、ベーコンに目玉焼きが乗っかり、それがつぶれて和えていかれる味覚がヌメヌメと再現される。
「嫌だ!私はスクランブル党だ!」
ぷわぷわのスクランブルエッグが回る。
「うわあああ」
「一旦入ったパルスは、自分のなかで微調整してください、データーがでないとまざっちゃいますよ」
ギソムが注意を促した。
「納豆送ってもいい?」
「どうぞ」
「納豆!」
ランドの脳裏に、何とも言えない味覚が襲ってきた。
臭い! いや、脳しかないのだから、臭いというのは正しくない!
粘りつく豆! 口のなかで、へばりつく糸! 噛もうとすれば、するりと抜けていく物体! その[感覚]だけが脳を走るのだ!
「こっ・・・・・これが納豆かあ」
かけない脂汗をかいて、ランドはようやくパルスを脳の中から削除した。喉があれば、ぜいぜいと音がするだろう。
「大丈夫ですか?脳波が乱れていますよ?」
ブルーハイムが、心配げにランドにパルスを送る。
「だっ、大丈夫です」
「あ、後デートの後によく食べた、アンかけダンゴ・・」
シソンはと言えば青春の記憶に、トリップしている。
「シソン博士は、日系のボーイフレンドがいらっしゃったようですね」
苦笑のギゾムであった。
「アンかけダンゴっ!」
アンかけダンゴである。ダンゴのぷにょぷにょした上に、あま〜〜〜いアンコが、ぬちゃばあああっとかかってるのを想像したまい。その感覚が、脳のなかでのみ完成されるのだ!
「どああああっ!シ・・・シソン博士えええっ!」
「あら、どうなさったの?ランドさん」
「わっ・・私は、アジア系の食事にあまり慣れていないのです」
よれよれのパルスで、ようやくランドは、思考を絞り出した。
「しゃあないなあ、宇宙の船乗りは」
かんらからと、ホルツァーが、笑いのパルスを送る。
「そんなこといったって」
むっとして、ランドはこらえる。
「私は整備工だからなあ。闇鍋なんか良くやったから、変な味には免疫あるのだよ」
ぐふふふふ、と笑っている。
殴りたくても殴れない・・、体がない己が身の不運を改めて再認識してしまうランドであった。
「じゃあ、西洋食にしましょうね」
同情してか、シソンは提供先を変える。
「コカコーラ!」
「チョコレートパフェ!」
ラクソンが先か、シソンが先か・・・そんなことはどうでも良くなってしまった。
パルスが混ざってしまったのである。
コカコーラの、あまあああい味の感覚に、炭酸のしゃわわわわあああっとした感触。チョコレートパフェの、まったりとしてそれでいて腰のない生クリームに、妙に甘いチョコのかけ合わせ・・・・。
「わっ、私は甘いものは苦手なんですっっ!」
ランドの悲鳴は、既に遅かった。
女性の、こと好きな食物に関する記憶というのは、驚く程ディティールが細かく再現される。
舌の上の生クリームが通る感触、喉を流れ落ちるチョコレート。過負荷でセキュリティーが発動し、各人のコネクターを一時カットするまで、ランドは生クリームのチョコレートパフェとコーラの海におぼれる自分の夢を見た。
それは、時間にすればコンマ1秒もなかったのだが、彼は、無くしたはずの彼の体で、その海の中を必死に泳いでいたのだった。
意識を復活させて、コネクターを元に戻した後も、彼の脳は、ばたついた感触だけは長く記憶に残していた。
つるかめ つるかめ