その例のひとつが「ケータイ」である。通話どころか各種データ通信が可能であり、様々な種類のフォーマットのデータをプレビュー可能な個人用携帯端末である「ケータイ」が特殊な装備ではなく、老人から小学生までも所有する一般的なアイテムとなった世界を、かつて予想したものがあったであろうか?
「ケータイ」のない時代では、待ち合わせにはかなり高度な技術が要求されたものである。万が一待ち合わせに遅れたり、待ち合わせ場所がわからないなどのアクシデントが発生した場合には、綿密な準備やどちらかの忍耐がない限り、再度出会うことが不可能だったといっても過言ではない状態であった。
それが、「ケータイ」の普及に伴い、待ち合わせというのはものすごくシンプルになった。かつてのようにすれ違いのないように、駅のどの改札を出て何本目の柱の前で待つなどというような細かい指定が不要になったし。万が一待ち合わせ時間に遅れるような事象が発生したところで、その場その場で連絡を取り合うことによりいとも簡単に再度待ち合わせることが可能となったのである。
また個人向けの連絡は相手がどこにいようとも、その個人の「ケータイ」に対してなされるため、特殊な状況でない限り呼び出してもらうといったことはめったになくなった。
SF小説がテクノロジーの発達で古臭く感じられるようになるのはよくあるが、この「ケータイ」が人々の行動様式を変えてしまった現在では、「ケータイ」普及前に書かれた小説は多くのものに古さや、違和感を感じるようになったのである。
これほど社会生活すら変えてしまった「ケータイ」であるが、その概念自体は単に「電話を持ち歩けるようにする+小型化して持ち歩ける情報端末」といったシンプルなものであり容易に想像がつきそうなものである。
しかも1980年代ではすでに「携帯電話」が実用化されており、そのサイズの小型化と普及さえ予測できれば、ある程度現在のような社会というのは類推できない方がおかしいのだ(と後知恵ならばいくらでもいえるのである)。
さて、それでは谷甲州は現代のような「ケータイ」が普及した社会というのを予測できていたのであろうか? 日本で「携帯電話」と呼ばれるサービスが開始されたのは1987年4月のことである(それ以前にも自動車電話や、ショルダーフォンなどのサービスは存在していた)。当然1988年1月に刊行された「36,000キロの墜死」であれば、我らが谷甲州であればすでに作品中にもごく自然に取り込んでいるはずである。さすがに「ケータイ」という今使われている用語までは予測できないとしても各自がパーソナルな携帯通信用端末を持って、いつでも通信できる世界を構築しているぐらいのことは予測しているはずだ。
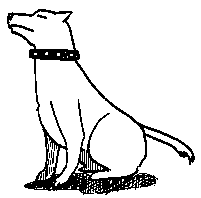 そう思って「36,000キロの墜死」をチェックしてみると、随所に「ケータイ」の普及による社会の変化を予測できなかったかのように見える箇所が何箇所か見つかる。
そう思って「36,000キロの墜死」をチェックしてみると、随所に「ケータイ」の普及による社会の変化を予測できなかったかのように見える箇所が何箇所か見つかる。だからと言って谷甲州が、「ケータイ」がこれほど普及するのを予測できなかったと判断するのは間違いである。
よくよく読んでみれば、表面上には出てこないだけで、「ケータイ」は作品世界にはしっかり取り込まれており、使う必要のない場面で使ってないというだけのことであったことが判った。以下、そのことを検証して行こう。
まず冒頭では、ダグが保安部にかかってきた事件の第一報を受けて広沢部長に受話器を回すシーンがある。
このシーンでは「ケータイ」は登場しなくて当然である。通報は保安部宛にかかってきたのであり、保安部の固定電話に着信があることになんの問題もないのである。
次に気になるのは以下のシーンである。
そういったとき、通信ユニットの呼び出し音がなった。ティモシェンコは、ユニットを取り上げてふたことみこと話していたが、それを部長に突き出していった。「保安部からだ。緊急の用件だそうだが…。」
一昔前ならごく普通のシーンであるが、今ではかなり気になる描写である。「ケータイ」が当たり前になった現在では、たとえ出先であっても誰かに電話をかけて取次いでもらうなどということは、非常に珍しいことになっている。緊急事態であれば、広沢部長のケータイに直接かければいいのになぜ取次ぎを頼んだのであろうか?
このシーンは南宙港の外壁にむき出しのまま係留されている作業船内の会話である。つまり軌道都市外の宇宙船の中であるから、通話圏外であってもおかしくない。おそらく保安部からの連絡は当初広沢部長の個人携帯端末に向けて送られたものの通信圏外であったために、再度部長が行っているであろう宙港ドッグに連絡をし、そこから連絡が回されたものと考えても何もおかしくないのである。
では次のシーンはどうであろうか?
ところが、すぐ後から歩いてきているはずの、ダグの姿が見えない。肩すかしをくらったエレナがみまわすと、樹の陰にかくされた公共通信ユニットの電話を取り上げたところだった。音声専用モードで、誰かと話している。その様子からして、相手は女友達のようだった。
これも現代から見れば、奇異に見える描写である。わざわざ、女友達に電話をかけるのになぜ、ダグは公共通信ユニットを使っているのであろうか?自分の個人携帯端末を使用すればいいのではないか?これはまさに谷甲州が「ケータイ社会」を予測してない証明になるのではないかと思う人もいるであろう。
だがこの数ページ後で、ダグはこの女友達から送ってもらったサイナス社の重役リストのハードコピーを公共通信ユニットから取り出している。つまり、ダグはハードコピーでデータを受け取りたいために公共通信ユニットを使ったのである。いくら携帯通信端末が進化した所で、ハードコピーに必要なリソース(特に紙などの消耗品)を限られたスペースに内蔵するのは困難であり、無駄である。そのため通常の通信は携帯端末を使っても、ハードコピーが必要になる場合に公共通信ユニットを使うのはごく自然なことである。
ただし、この説明はハードコピーが必要な状況があってこそ成立するものである。「ケータイ」で各種データが閲覧可能となっている現在、写真やリスト程度のデータであればデータそのものを端末間で転送して、端末に表示させ参照するというやり方が当たり前になっており、ハードコピーはよっぽどのことがない限り必要とはされていない。ハードコピーを必要とする状況自体が簡単にいつでもデータをプレビューすることができない状況を前提にしたもの、つまり携帯端末がない世界であるのではないかということも考えられる。
しかし、電子的データは容易に複製が可能である。ダグのような保安部員が扱うデータが無制限にコピーされることは各種の問題が発生する。そのようなデリケートなデータを取り扱うにはむしろアナログ的手段でしかコピーが困難なハードコピーとしてデータを持ち歩いた方が管理が容易なのである。
本作品内でデータを自己の携帯端末に複製することなく、やたらとハードコピーを使いたがるのは、上記の様な保安上の理由であると考えられる。
ダグがわざわざ公共通信ユニットを使ってデータのハードコピーを取っていた理由はこれで説明がつくが、次のシーンはどうだろうか?
ダグは、足をとめた。さっきの男にまちがいなかった。妙な話だが、彼を追いかけてきた男を、今度はダグが必死になって追いかけていたのだ。その男は、公共通信ユニットでどこかと連絡をとっていた。
今度は、サイナス社の警備課の男が連絡をとっている場面である。どう読んでも、ハードコピーが必要な場面ではない。わざわざ公共通信ユニットで連絡をとる必要がどうしてあるのであろう。このような場合は普通は「ケータイ」で連絡するはずである。そしてその直後のシーンでは
ダグは恐ろしい形相で、男をにらみつけた。男は、奇妙な声をあげてあとじさった。ダグはもう、その男に興味はなかった。遠巻きに見ているジョガーの視線を背中に受けながら、ダグはオフィスに連絡をいれた。もしもマックスじいさんしかオフィスにいなければ、ダグ一人でやるしかない。ところがいきなり広沢部長の大声が飛び込んできた。
と書かれており、わざわざ公共通信ユニットを使ったとの記載はない。ごく普通に「ケータイ」で連絡を取ったと思われる。つまり、前のシーンはわざわざ公共通信ユニットを使うことを強調したかったのである。
ではなぜ公共通信ユニットを使ったのであろうか?「ケータイ」を持ってないというのはまず考えられない。バッテリー切れであれば、それなりの記述があるであろう。直後にダグが通話していることからも圏外でもないだろう。「ケータイ」が使えなかったのではなく、公共通信ユニットを使わなければならないなんらかの理由があったと考えるのが妥当である。その理由として考えられるものの一つとして、大画面の高精細なデータを参照したかったのではないかということがある。たとえどんなに「ケータイ」が高性能になったとしても、そのフォームファクターから画面サイズにはある程度の制限が加えられる。たとえばこの状況のように、相手を追跡中の状況で連絡を取り合う場合には、ある程度大きなマップを表示することはかなり有用である。もちろん「ケータイ」であっても縮尺を変えて表示すれば広い範囲のエリアを表示することは可能であるが、その場合では細部が確認できなくなり、細部を確認しようと思えば、全体が見えなくなる。これが公共通信ユニットの大画面であれば広範囲を詳細に表示することが可能となるのである。短時間で広範囲の状況を確認しつつ、必要な細部の情報を確認するにはやはり「ケータイ」では不十分なのである。これがダグをおっかけている最中であれば、大画面のメリットよりも移動しつつ連絡ができる「ケータイ」で連絡を取り合っていたであろうが、この場面ではダグを見失っており、一旦体制を立て直すことが必要であったのであろう。それであれば大画面のマップで他のメンバーの探索情報や潜伏しそうな情報を一度に確認しようと思うのも当然である。
というようなわけで、この場面でも「ケータイ」がなかったのではなく、「ケータイ」よりも公共通信ユニットが有用だから使っていたにすぎないと考えられる。
たとえ「ケータイ社会」を予測できていたとしても、むやみやたらとそれを前面に出さないあたりというのが、やはり谷甲州の奥深いところなのであろう。
