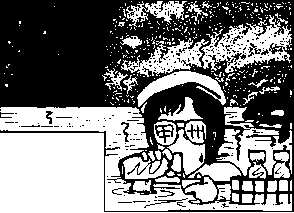谷 甲州
さて困った。感想を書こうとしても、なにも出てこない。正確にいうと、書きたくても記憶が曖昧すぎて何も書けないのだ。夕方の6時に乾杯したと思ったら、いつの間にか次の日の朝になっていて、「これで終りです」といわれたようなもので、間の記憶がすっぽりと抜け落ちている。
部分的にいうと、松本富雄が対談の最中にマイクをふりまわしていたり、酔っ払った石飛卓美がだれかれなしにチキンウイングフェイスロック(それとも千鳥だったか?)をかけていたり、酔いつぶれた誰だったかが自分のポケットに突っ込んだのを忘れて「俺の腕時計はどこにいった」と捜しまわっていたり、宴会場のまん中に布団をひいて寝てしまった奴がいたり、そんな人たちを横目でみながら(酒のみって、やーですねえ)眉をひそめてつるかめつるかめといいながらおとなしく酒を飲んでいた自分は思い出すのだが、全体的な流れというのがよくわからない。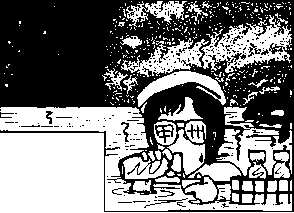
これはきっと、ケーブルカーの駅を降りて狭い坂道を登り下りするうちに、体の中の生物時計が狂ってしまったためだろう。さもなければ時空の狭間に落ち込んで、午後6時から翌朝8時までの時間が消失したのかもしれない。どう考えても、「乾杯」から「これで終りです」まで直通だったような気がして仕方がない。生駒の神さんが、危険回避のためにバイパスをつくったのかなあ。
もしかすると真相は「あまりに楽しかったので、時間のたつのを忘れてしまった」のかもしれない。そういえば、おみやげに玉手箱をもらったような気もするが、それもさだかではない。帰り道に宝山寺の参道を歩きながら、生駒山ー邪馬台国の話をした記憶があるが(宇宙戦艦ヤマタイだったかな)生駒−竜宮伝説くらい実在するかもしれんなあ。不思議。不思議。
<谷甲州氏へ 眉村卓>
ぼくが初めて谷甲州氏の作品と出会ったのは、例のチャチャヤング−深夜放送への投稿としてである。この番組をぼくが担当した第一回は1970年9月3日〜4日であった。ショートショートコーナーは、それからだいぶ経ってできたのだから、その以前ということはあり得ない。チャチャヤングが約二年で終わる迄、随分多くの人が作品を寄せてくれて、谷甲州氏もそのひとりであった。
番組終了後、この投稿者の有志が中心になって会がつくられ、書き手が何人か誕生したことは、ここでいろいろ述べる必要もなかろう。
谷甲州氏はそうした中にあって、当初、正直いってあまり目立つ存在ではなかった。ただ、結構執念深いというか底力のある書き方をしていたのが、印象に残っている。きらきらすることよりも構成に重点を置くタイプだったようだ。
この谷甲州氏がじりじりと力をつけ、海外生活体験も重ねるうちに、いつの間にかSF山脈の一角に突兀(というのがふさわしいのではないか)と位置を占めるに至った。しかるべき評価も受け、蓄積も増え、固定読者もできている。努力の成果である。敬意を表したい。
もっとも、作家生活十年というのは、プロの世界ではどうやら一人前の列に入りつつあるというところで、この意味は谷甲州氏自身が一番よくご存じだろうが、大きな勝負はこれからであり、自己鍛練をも含めてのさらなる努力が要求される時期なのだ。
谷甲州氏は、持ち前の着実な進み方とファイトで、きっと前進を続けるであろう。ひいき目にではなく、相当な悪意を持った観点からも否定し得ない。画然としたおのれの世界を築きあげるに違いない。これ迄の氏の経歴を考えるとき、どうしてもそうでなければならないのだ。
ときには休息も必要である。息切れしないために。
しかし永い休息は危険である。そこに居すわる気になってしまうから。
好漢、今や大股に進むべし。
<春季甲州祭に寄せて 虚弱SF作家・会社員 堀晃>
谷甲州氏は今や日本最強のSF作家である。世界でも屈指の存在であろう。向うところ敵なし、破竹の進撃を続けている、恐ろしい作家である。
最強とは腕力を指す。腕っ節の強さであり、つまり喧嘩の強さといってもよい。
谷甲州出現までは、眉村卓氏が最強であったと思われる。もっとも両者決闘の上で順位が決まったわけではない。眉村さんは温厚な方だし、甲州氏も別に肉体的な戦いを挑む理由はないから、差しで勝負してどちらが強いかの判定は不能である。
谷甲州氏を最強のSF作家と判断する理由は、その背後にいる軍団の恐ろしさにある。つまり「甲州組」と「人外協」の存在である。このふたつの組織がどんなものかは知らない。ただ恐ろしい噂ばかりが聞こえてくる。谷甲州氏をカシラと仰ぐ屈強な男どもや人間とは思えぬ猛者や明らかに人間ではない存在までが徒党を組み、かれらが通り過ぎた後には一滴の酒も残っていないという。
この一群が厳寒の生駒山頂で一夜の酒宴を張るという。どうか酔余の勢いで山腹を駆け降り大阪の街を侵略することになどなりませぬよう祈るのみであります。
ま、しかし、この軍団ある限り、谷甲州氏はまぎれもなく最強のSF作家でありましょう。
最近はその腕力が筆力に転じつつあるようで、頼もしい限りであります。
<谷甲州に捧げる谷甲州のバラード 石飛卓美>
谷さん。
ぼくはいま寝そべりながら、あなたの栄光の軌跡をひもといています。SF作家、谷甲州がどのようにして誕生したのかを。産道を通ってうぶ声を上げた時から、あなたは輝いていました。
いまここに一冊の本がある。
奇想天外1979年3月号である。
この号において我等の谷甲州は誕生したのであった。
第2回奇想天外SF新人賞佳作「137機動旅団」。
選評を読むと、まず筒井康隆氏が絶賛している。小松左京氏「自衛隊に入ったのかな、この人は。たとえば戦闘命令なんか非常に鮮やかだもの」。星新一氏「ヨコ書きという非常識を侵しているにしては、内容はガッチリしてる。この中では一番うまいですね」
筆名は甲州(まだ谷という姓はついていなかった)。おまけに応募作は横書きであったらしい。結局三作が佳作だったけれど、甲州以外の人はいまや見る影もない。
十年前、ぼくはこの「137機動旅団」を読んで感動した。その頃のぼくといえば、作家を志してもいなかったし、趣味でショート・ショートを書くくらいだった。町会議員という仮面をかぶってたので、コンベンションに参加したこともなく、隠れSFの典型だった。1951年生まれはぼくと同じである。ぼくに夢と勇気を与えてくれたのが、ほかならぬ谷甲州だったわけだ。
8月号に第二弾「ガネッシュとバイラブ」、翌1980年11月号から「C・B−8越冬隊」が連載された。のちに「惑星CB−8越冬隊」として刊行される。81年4月号で、ついに航空宇宙軍史「星空のフロンティア」が登場する。筆名も谷甲州となった。
デビュー作の時に、もう航空宇宙軍史の構想があったというからおそれいる。
その後は誰もが知っている活躍。人気においても、若手作家のベスト3に入る。
やっぱりそれは、作品もさることながら、谷甲州氏の人柄によるものだ。頼りがいがあり、ぶっちゃけていて、うさんくさくなく、親しみがあり、いい男(あまり褒めると嘘くさくなるな)である。
谷さん、10周年おめでとうございます。けれど、10周年はひとつの通過時点にすぎないでしょう。
これからも面白い作品をどんどん発表して、90年代、平成年代を代表する作家になってください。
<酒豪谷甲州について 松本富雄>
谷甲州、永瀬唯、僕の3人がバハイ・プルバをつくっていた頃、近くに「SFの本」のスタジオ・アンビエントがあって、そこの社長新戸雅章さん、現在は湘南ドラゴン伝説シリーズの新田正章に変身
や、当時アンビエントを手伝っていた能なしワニシリーズの中井紀夫さんなんかと、みんな酒が好きなものだから、よく飲み会をやっていたんだけれど、段突に強いのは、まあ体力もそうなんだけれど、谷甲州なのだ。
その甲州が一度だけ前後不覚になって吐いたことがあった。
それも僕の背中に。
あれは今から6・7年前、国際協力事業団のプロジェクトで、フィリピンにわたる前の頃のこと、SFセミナーがあったときで、その晩、僕たちは女の子をふくむ4人で、新宿ゴールデン街の「NOV」というスナックで酒をしたたかに飲んだ。
ところが、体力抜群の甲州がメロメロに酔っぱらっちゃって、ほとんどかつぐようにしてタクシーに乗せ、SFセミナーの合宿所へむかった。それで合宿所へ到着する寸前になって、谷甲州が僕のダブルのスーツの背中に吐いてしまったのである。
それからまもなくして谷甲州は奥さん同伴でフィリピンへ渡ったんだけれど、一時帰国したとき、しっかり子供をつくってきたのだ。
で、僕は納得したのだけれど、あれほど酒につよい甲州が吐いたのは、きっと男のツワリだったのだ。
デビュー十周年おめでとう。
<トーポリってどんな樹 柊たんぽぽ>
前略、今晩は。暑中しょっちゅうお見舞申し上げます。越夏隊ごくろうさん。とはフィリッピンにだしそびれた手紙。で、惑星を探していたら月や太陽と同じ軌道であるのに思い至った。正確には知らないが。たまに始発の地下鉄に寝ながら乗ると、電車は地球の表面から地下に潜っていき、甲州の惑星の坑道のはなしを思い出す。ハードボイルドにはいま一つ興味がない。非SFではサバイバル冒険ものに期待したい。谷甲州は組織を書ける日本で数少ない作家だ。仕事の面白みを書ける人だ。これは日本文学がほとんど手つかずのところある。はっきり知らんが。ノンフィクションがかろうじてこの分野をカバーしている。たぶん。法人は超人。外国語の勉強は知らんが日本の古典も読んでるか、そうすれば鬼に金棒だ。失礼。十年になるか。センス・オブ・ワンダーやな。他の連中と同じ頃や。作家やっているのはロマンや。これは大変なことなのだろう。近すぎて見えない。頓首。

 春季甲州祭レポートへ戻る
春季甲州祭レポートへ戻る